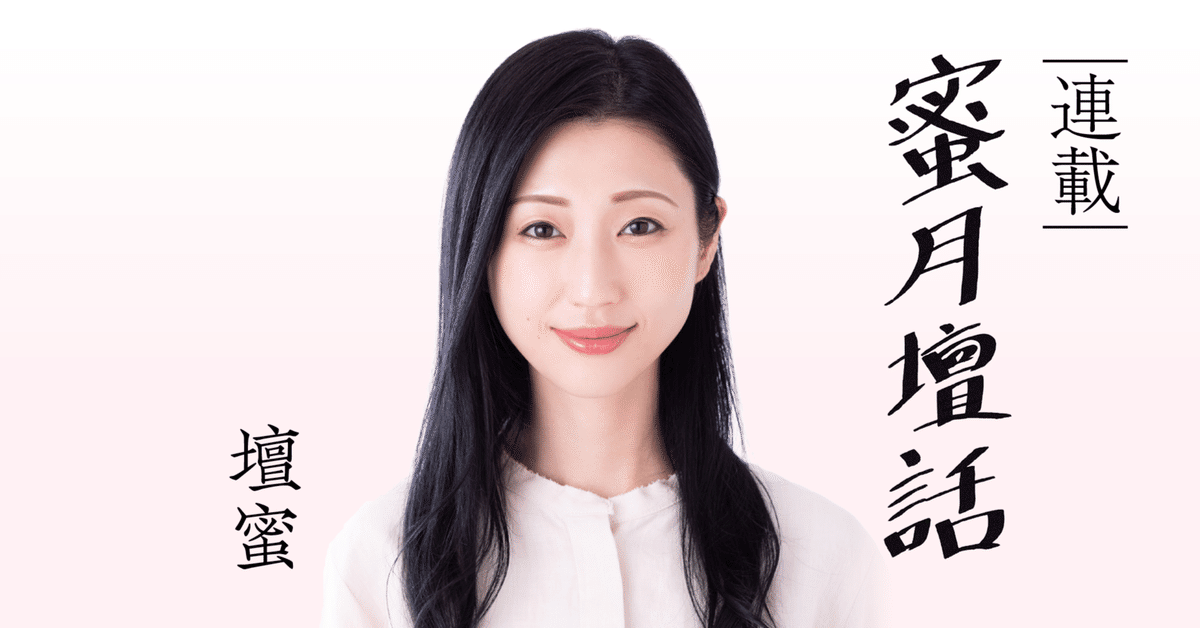
「将来」を描かなかった理由はここに。「芸能関係者の考える“新人はこんな感じ”ではなかった新人時代」――お題を通して“壇蜜的こころ”を明かす「蜜月壇話」
タレント、女優、エッセイストなど多彩な活躍を続ける壇蜜さん。ふだんラジオのパーソナリティとしてリスナーからのお便りを紹介している壇蜜さんが、今度はリスナーの立場から、ふられたテーマをもとに自身の経験やいま思っていることなどを語った連載です。
*第1回からお読みになる方はこちらです。
#10
芸能関係者の考える「新人はこんな感じ」ではなかった新人時代
ある女性タレント(私が20代後半のときにこの話を聞いた際、彼女は40歳手前だった)が、少し年上の夫との価値観の違いによる、たび重なる口論やぶつかり合いにくたびれ果てて離婚した、というニュースを耳にした。お金持ちの旦那さんを見つけて、盛大な式をあげて5年もしないうちに、とワイドショーの辛口なコメンテーターやレポーターに言われていたが、夫婦のことはやはり夫婦にしかわからない。彼女たち的には「5年の間になんとかならないかと模索したが無理だった」故、5年めにしてやっと出た結論だったのかもしれないし、「憶測で意見したらいけないよなぁ」とコメンテーターたちに対して思っていた。憶測で意見するのも彼らの仕事の一部であり、私自身もそういう仕事を請け負って飯のタネにすることになるとは当時想像も予測もしていなかったが。
離婚した件の女性タレントは、後々ある週刊誌のインタビューを受けていた。つらさもやや薄れ、己が反省すべき点もあったし、今では相手の幸せを願うくらいにはなったからインタビューの依頼を受けたと綴られていた。元夫に暴力はふるわれていなかったらしいが、口論の際に随分といろいろなことを言われ、言い返すこともできないほどだったという。いわゆる「言葉の暴力」を受けたのだろうか。なかでも記憶に残っているのが、「おまえ(その女性タレントのこと)は人をイラつかせる天才だな、俺を怒らせる才能は世界一だよ!」となじられたというコメントだった。そんなことを言われたら、私もショックでどうしていいかわからなくなるだろう。彼女もまた、その言葉を吐き捨て、出ていってしまった元夫の背中を見ていることしかできなかったという。「私が彼のすべてのイラつきの原因?」と考えたら悲しくなって、自分を責めたり眠れなくなったりと不安定な日々が続き、元夫を恐れるようになったらしい。ワガママを聞いてもらっている自覚はあったし、対等な話し合いやいわゆる痴話げんかはよくあったが、段々と受け身で責められるだけの夫婦げんかに仲直りや終焉の兆しが見えなくなり、離婚の運びになったと彼女は記者にコメントしていた。元夫の意見を聞くことはできないが、「イラつかせる天才」なんて本当に言われたら、修復や再構築は難しいのではないかと感じた。ちなみに彼女が語るこの記事に異様にシンパシーを覚えたのは、当時私も付き合っていた男性にデート中、「よく僕が怒ることばかりできるね」と言われて、けんかにならないほどショックを受けて泣いてしまったところ、「自分の過失なのに泣くの? キミは被害者なの? 泣きたいのはこっちなんだけど」など追いうちをかけるようにさまざまな言葉を言われた日があったからかもしれない。その人とは3年弱付き合い、別れた。私にもいたらない部分はあったが、好きな人が恐い人に変わってしまったから仕方ない。
窮屈な束縛や、恐怖を感じる言葉のやり取りから解放された私は、多少のショックを引きずりつつグラビアタレントの仕事に打ち込むようになった。仲間のタレントたちが歌手や女優、モデルなどにコマを進めるステップとしてのグラビア仕事だと言うなか、私は「将来? わからないなぁ」と言いながら、「今もらえる仕事」と向き合った。先に何かがあるとは思えなくなっているあたり、自分を大切にして目標を持つことを良しとする気持ちが、元彼とのいざこざもあってフタをされてしまったようだった。タレントとして生きられるとは、自分がいちばん「それはないな」と思っていたので考えられなかった。自分を否定しまくりの人間は、どこかあきらめているような気持ちがあるせいか、グラビア仕事で過激な衣装を渡されても煽情的なポーズを求められても、あるいは性的なイメージを持たれるようなシチュエーションでの小芝居を頼まれても、「まあ、いっか。グラビアとして求められているし、見ている人が喜ぶなら」と割り切れてしまう。周囲のグラビアタレント仲間から「脱いだりしたら先がなくならない?」と言われても、「先は最初からないようなものだし」という考えが抜けず、「そうかなぁ、そうかもね」とヘラリと返した。
仕事をともにしたカメラマンや編集殿からは、「この先どうするか、こんなに曖昧な人はめったにいない」と言われた。それは揶揄でもバカにされたわけでもなく、ただ彼らは驚いていたのだった。「~になりたい」「○○さんみたいになりたい」的な話を、新人グラビアタレントたちからたくさん聞いてきた彼らにとって珍しかったのだろう。母とかわした「3年活動して売れる兆しがなかったらあきらめる」という約束もあったため、また派遣社員としてどこかで働くかもしれないと言い足したときも驚かれた。
芸能の世界で生きたいと志望して飛び込む人々は、いつか叶えたい目標やなりたい自分を持っている。私もそれは多くの芸能人の卵にあてはまると思っていた。当時芸能人志望とは言い切れなかったから、周囲がひくような仕事も勇んでできたのかもしれない。芸能関係者がイメージする「新人の姿」とはどうも違ったが、それが29歳を過ぎてグラビア仕事を始めた私の個性だったようだ。
プロフィール
壇蜜(だん・みつ)
1980年秋田県生まれ。和菓子工場、解剖補助などさまざまな職業を経て29歳でグラビアアイドルとしてデビュー。独特の存在感でメディアの注目を浴び、多方面で活躍。映画『甘い鞭』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『壇蜜日記』(文藝春秋)『たべたいの』(新潮社)など著書多数。

