
胃弱と文学とチャーハンと(英米文学者・阿部公彦) 【前編】
英米文学研究から文芸評論まで幅広く手がけ、「名作いじり」「事務」などユニークな視点の著書の多い、東京大学教授の阿部公彦さん(57)。「胃弱と文学」もテーマの一つで、「100分de名著」(NHK)では夏目漱石の作品を「胃弱」を通して読み解き異彩を放ちました。「胃弱の文学」とは? 胃弱と文学とチャーハンの関係は?
■「胃弱」をネタ化する漱石『吾輩』の猫

──文学への「食」のアプローチでは、「美食」「料理」「空腹」などの視点からはありましたが、「胃弱」からの読み解きは珍しいのではないでしょうか。
私が「胃弱と文学」に興味を持つようになったのは、夏目漱石がきっかけです。ご存じのように漱石は自身が胃弱で、胃潰瘍を悪化させて亡くなりました。
ただ、彼は生まれながらにして虚弱体質で胃が悪かったわけではなくて。ステーキや甘いものが大好き。ひょっとすると幼児体験と関係あるのかもしれませんが、食べ物に関するセルフコントロールがやや利かない感じで。それで胃を悪くしたようにも見えます。
亡くなる引き金になったといわれるのは、好物の「砂糖がけの南京豆」。招待された結婚式の食事で、普段だったら「胃に良くない」と制止する妻の席が離れていたのをいいことにバクバク食べてしまった。
──漱石の作品にも「胃弱」の人が出てきますね。
胃弱や胃病の人は、作品に多く登場します。
デビュー作『吾輩は猫である』では「胃弱」の言葉が過剰に出てきますし、猫は「胃弱」をネタ化さえしている。『道草』では主人公を取り巻く気持ちの悪い状況と胃の不快感が連動し繰り返されます。
では、漱石自身が胃弱だったので、たまたま作品に書かれたのかというと、それだけにとどまらない。その奥にあるものを漱石の宿敵である正宗白鳥が言い当てています。
■明治の作家がこぼす「肺病に比べ胃弱は地味」

──胃弱の奥にあるもの?
白鳥は、文学者には「胃弱派と肺病派がいる」と言います。
肺病というのは結核ですね。そして、白鳥自身も胃弱でした。家系的に。
で、「結核は天才の病」だと。
実際、結核で亡くなった作家には正岡子規や堀辰雄、ジョン・キーツなどがいます。
加えて、結核は喀血するなどドラマチックで、微熱の続く状況が創作の呼び水になり、ロマンチックでもある。
ところが、これに対して胃弱は「地味で、元気がなくて、ぱっとしない」。
──胃弱は外からは見えづらいですし、トホホ感が伝わってきますね。
白鳥は、自分は漱石のことをさんざん批判してきたけれど、「胃病で亡くなったことに関してだけは同情する」。胃病の「すごく現実的でみみっちい感じが、漱石のリアリティをなしている」と指摘します。
また、死期の迫った漱石が「死んじゃ困るから、注射を打ってくれ」と言ったのを捉えて、「どん底の心の声が聞こえて、変にサービス精神旺盛な小説よりずっといい」と褒めたりします。
「どん底の心の声」という言い方には、どこか「腹」や「胃」に人間の本質を見ようとする態度があるように思えます。
さらに、胃が弱いっていうのは、豪快さとか、豪胆さとか、体力とかとは正反対。ジェンダー的には「男性性の欠如」にもつながる。そのことを明治の時代に、白鳥は既に見抜いていたのです。
■「嘔吐」は大江健三郎が先駆け

一方、ジェンダーの視点で見るなら、最近の気鋭の女性作家たちの作品に主人公が「吐き気」がしたり「実際に吐く」ものが多いことが気になっています。例えば、本谷有希子とか絲山秋子とか。女性の抑圧されている状況が積もり積もって、「吐く」という生理的な反応として出ているのか。
もちろん、男性でも「嘔吐」を書いている人はいます。
「嘔吐」というとサルトルを思い浮かべる人は多いかと思いますが、大江健三郎も「吐く」シーンをよく書いています。
明治、大正の頃は汚物とか、体の分泌物は表に出すべきものではないとして、小説に書かれることはありませんでしたから、大江は先駆けではないかと思います。
──体が魂の叫びを表現してしまう。言葉にしなくても、生理的に表れてしまうということでしょうか。
文学は、まさに言葉にならないものを表現するものですから。
そして、ある種の作家は言葉にならない微妙な感覚をつかまえるのがうまく、それが生理的な表現として表れているのではないかと思います。
また、表に「出していいもの」と「出すべきでないもの」。「公」と「私」の規範は近代の特徴の一つですが、それが確立されるにつれ、人はむしろ「見えないもの」や「隠されているもの」、すなわち他人の「腹の中」「心の内」をより見たくなる。そのせめぎ合いの中から近代小説は生まれました。
そういう意味では、生理的な反応は「心の奥」を覗くための格好の入り口なのであり、小説らしい目のやり方を助ける装置だと思います。
■「ムカつく」「キモい」──進化し続ける「胃」発の表現

──最近では「嫌だ」「許せない」といった時に「ムカつく」「キモい」の言葉が使われます。これも「胃」発の表現ですよね。
以前は、「くだらねえ」「腹が立つ」「頭に来る」といった言葉が主流だったのが、「ムカつく」が登場し、最近では「キモい」が若者を中心に使われています。
胃は「心の鏡」ともいわれ、連綿と胃的な表現がつながっているといえます。
──「腹が立つ」より「ムカつく」「キモい」の方がより生理に刺さる感覚がありますね。
「体の声を聞こう」「生理的な反応は正直だ」といった社会の風潮も関係していると思います。
だれかが「ムカつく」と言った時に、実際には胃はむかついていないことが多いと思いますが、不快表現として認知する土台が近代社会にあって。それはアンチ・インテリみたいな部分から来ているのかもしれません。
また、ここ20年ほど「体は正直である」「体の声を聞こう」といった風潮が強まっています。だから、例えば「胃が痛い」と言った時に「きっと何か嫌なことがあったのだろう」と人は想像しがちです。
しかし、果たして体は本当に「正直」なのでしょうか。
ひょっとすると体は野蛮なだけかもしれない。理性的に対応することの方が大事っていう見方だってあるはずです。
そういった意味では、「体は正直である」の風潮と「ムカつく」「キモい」の出現が重なっていることの根は深いと思います。「ムカつく」「キモい」の言葉はその前提があってこそ成り立っているわけですから。
■チャーハンは祝祭的
──ちなみに阿部さんは胃弱ですか?
胃弱というほど弱くはないですが、「胃強」ではない。
ちょびっと「弱い」感じです。
──となると、チャーハンってどんなイメージですか?
ある種、祝祭的な感じがしますよね。ご飯とおかずが一緒になっていて。店によっては作るプロセスも見れて、カーニバル的な余韻を感じながら食べる。それが、チャーハンの楽しさであり持ち味ではないでしょうか。
──では後編では、ちょびっと胃弱な阿部さんが普段どんなチャーハンを食べているのか、引き続き伺わせてください。
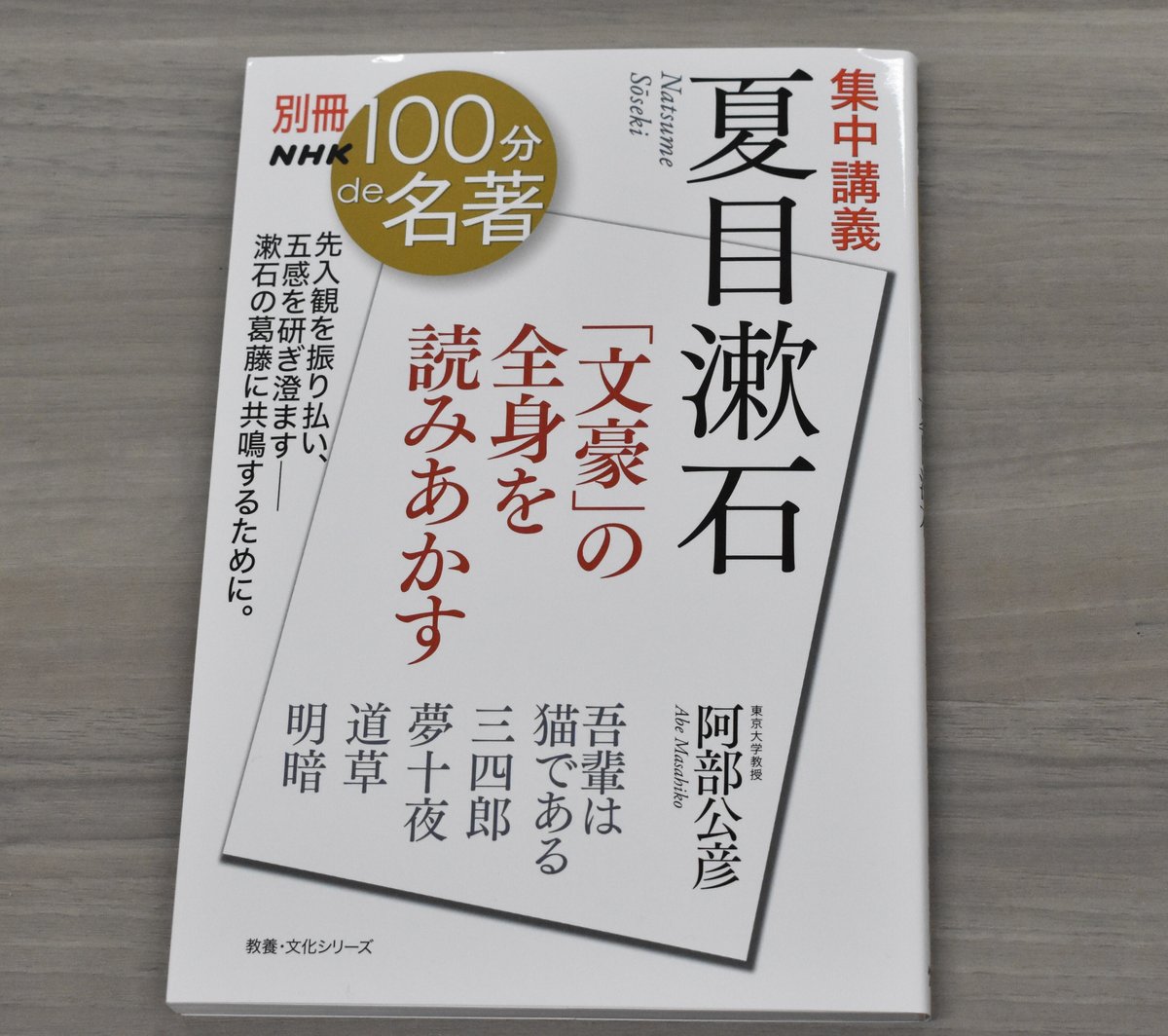
←第13回(稲垣えみ子さん後編)を読む
第15回(阿部公彦さん後編)に続く→
◆連載のバックナンバーはこちら
◆プロフィール
英米文学者 阿部公彦
1966年横浜市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授。東京大学文学部卒。同大学院修士課程を経て、ケンブリッジ大学で博士号取得。英米文学研究と文学一般の評論に取り組む。近著に『事務に踊る人々』(講談社)、『集中講義 夏目漱石 「文豪」の全身を読みあかす』(NHK出版・別冊100分de名著)、『文章は「形」から読む ことばの魔術と出会うために』(集英社新書)など。
取材・文:石田かおる
記者。2022年3月、週刊誌AERAを卒業しフリー。2018年、「きょうの料理」60年間のチャーハンの作り方の変遷を分析した記事執筆をきっかけに、チャーハンの摩訶不思議な世界にとらわれ、現在、チャーハンの歴史をリサーチ中。
題字・イラスト:植田まほ子

