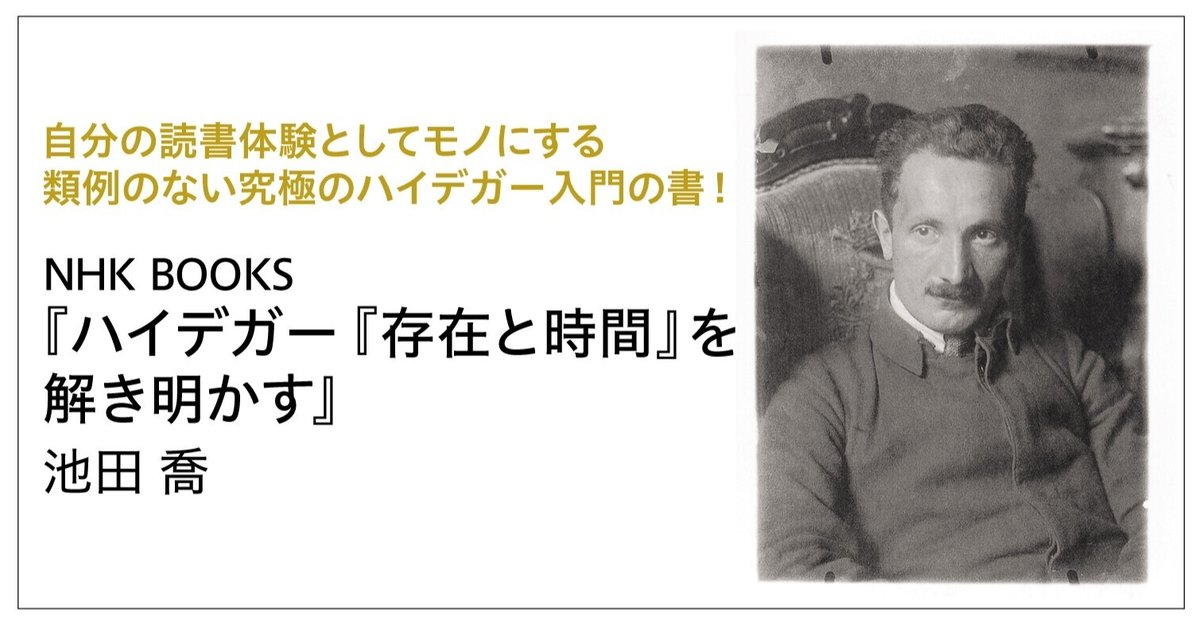
「これは、まぎれもない哲学書である」――【古田徹也寄稿】『ハイデガー 『存在と時間』を解き明かす』について
新刊『ハイデガー 『存在と時間』を解き明かす』の売れ行きが好調です。著者・池田喬さんと十数年の親交をもつ盟友・古田徹也さんに、この本を紹介していただきます。今年の春、古田さん著『はじめてのウィトゲンシュタイン』を池田さんに紹介していただきましたが、今回はその逆をやっていただきました。こんな本が出たら読まない手はないだろうと思わせる、魅惑の紹介文を掲載します。
本書はまずもって、『存在と時間』についてのとても分かりやすい解説書である。
現代の古典『存在と時間』は、二十世紀最大の哲学書であり、その後の哲学界全体に計り知れない影響を与えている――この評価に異を唱える人は誰もいない。しかし、その中身はひどく捉えがたいように思える。
『存在と時間』は〈存在とは何か〉ということを問う書物らしい。そこでは、存在の意味が時間という観点から問われているらしい。しかし、これはそもそもどういう問いなのか。さらに、ハイデガーは、存在の意味を問うためにはさしあたり私たち人間の存在の意味を問わなければならない、と言っているらしい。なぜだろうか、それは人間中心主義みたいなことなのだろうか。
本書が素晴らしいのは、こうした根本的な疑問、最初の引っ掛かりそれ自体に丁寧に向き合って説明してくれているところだ。
本書の工夫は、目次を見ただけでもすぐに分かる。各章のタイトルがすべて「問い」の形になっているのだ。『存在と時間』の構成通りにそのまま内容を辿りつつ敷衍するという、いわゆるコメンタリーの形式をとるのではなく、読者が当然抱くであろう諸々の問いを入り口にして、『存在と時間』という巨大な建築物にさまざまな角度からアクセスし、そのなかを自在に歩き回るのが本書の特徴だ。それによって、『存在と時間』をただ通読するのではなく、内容を実際に理解することができるのである。
また、この辺りでそろそろ具体例が欲しい、という箇所でそれがちょうど示されているのも、本書の魅力のひとつだ。
ハイデガーの抽象的な言葉遣いや議論の運びをかみ砕く文章が続き、掴み所が見えなくなりそうなとき、本書はいつも具体例を交えて説明を重ねてくれる。しかも、その具体例の息が長い。大工が釘でハンマーを打つという、『存在と時間』のなかでも用いられている例のほかに、台風に備えて窓ガラスに養生テープを貼るという例も、さまざまなトピックを横断するかたちで長く使われている。そのため、トピックの間の連関も見出しやすくなっている。
さらに本書は、一線のハイデガー研究者ならではの仕事が随所に認められる。たとえば、『存在と時間』以外のハイデガーの著作や講義録などもときに参照しながら、常に一定の脈絡のなかにハイデガー用語を置き、解説してくれる。そのような厚みのある解説は、ハイデガーの原典を広く深く読み込んでいる専門家にしかできないことだ。
内容面についても簡単に触れておこう。本書の特に前半は、私たち人間の日常生活をめぐる卓抜な「技能の現象学」を展開する著作として『存在と時間』を捉える視座を有しており、これは、ヒューバート・ドレイファスの名著『世界内存在――『存在と時間』における日常性の解釈学』(門脇俊介監訳、産業図書、2000年)と共通するものがある。
しかし、この研究書が『存在と時間』第一部第一篇の解釈に終始し、第一篇と第二篇の接続が全く見えなくなっているのに対して、本書は、その接続を見事に行っている。
第二篇で展開されている〈死への先駆〉や〈自己固有な自己〉、〈良心の呼び声〉といったテーマは、第一篇で輪郭づけられる日常性からの変様としてはじめて理解されうる。その理由を説得的に示し、変様の次第を詳しく描き取る本書の筆致は、実に濃密でスリリングである。
* * *
そして本書は、『存在と時間』の見通しのよい解説書であるだけではなく、この哲学書を糧に練り上げられた、紛れもない哲学書でもある。
哲学というのは本質的に「自分ですること」であり、本を読んで知識や雑学を仕入れるだけでは「哲学した」ことにはならない。かといって、まったくの徒手空拳で「哲学できる」人などいない。かのウィトゲンシュタインですら、フレーゲ、ラッセル、ムーア、ウィリアム・ジェイムズ、さらにはゲーテやフレイザーといった先達の議論を批判的に検討しながら、思索を重ねた。まして、ハイデガーは古来の哲学史に深く精通しており、『存在と時間』も元々はアリストテレスのテキスト解釈の書として構想されたという。ハイデガーは、古典の読解を通じて独創的な哲学書をつくりあげたのである。
本書は、その『存在と時間』を読解するという行為を著者の池田さんが実演してみせるものだ。そして、私たち読者は、その池田さんの読解をさらに読解することを通じて、「哲学すること」へと入ってゆくことができる。その意味で、本書はたんなる解説書や入門書ではなく、繰り返すように、紛れもない哲学書である。つまり、「これ一冊読めば、『存在と時間』を読んだフリができますよ」という代物ではない。本書は、『存在と時間』を読むことの本当の意味を教えてくれるのである。
本書の冒頭近くに、「『存在と時間』は、読者にこの作品の鑑賞者であることを許そうとしない」という印象的な一節がある。本書もまた、『存在と時間』を読み解きながら哲学することを実践し、読者を哲学することへと誘う本になっている。「許さない」というと厳しい感じもするが、実際にはもっと積極的で、楽しいことだ。なにも、読者に厳しい要求を突きつけているわけではない。本書も、それから『存在と時間』も、たんなる鑑賞者の立場から我々を連れ出してくれる本なのだ。
特に本書は、その丹念な記述によって、読者のなかに哲学的な種類の問いや観点を芽生えさせ、それについてさらに考えるように促してゆく。鑑賞者の立場から解放され、普段は活性化していない頭の部分が駆動し始め、物事に対する新たな見方が見えてくること――それは、哲学以外ではまず味わえない種類の醍醐味であり、喜びである。
では、本書は具体的にどういう風にして私たちを「哲学する」ことへと連れ出してくれるのか。問い自体の中身、組み立て方、議論の運び方――ほかにも様々な要素を指摘することができるが、本書に関してとりわけ重要な特徴と言えるのは、翻訳の検討という、哲学の研究者が普段行っている作業を再演しているという点だ。「現存在」、「世界内存在」、「配慮的気遣い」、「被投性」、「被投的企投」、「本来性」等々、『存在と時間』の様々な術語にあてられた従来の訳語を実際に吟味する様子を見せることによって、読者の思考を強く刺激するのである。
いくつか例を挙げよう。たとえば『存在と時間』における代表的な術語のひとつであるEigentlichkeitは、従来は主にauthenticityや「本来性」などと訳されてきたが、本書ではこれらの訳語の問題が周到に説かれ、ownnessや「自己固有性」という訳語が代わりに提案されている。
また、Umweltの訳語に対しても、かなり息の長い解釈を通して、「周囲世界」よりも「環境世界」の方が適当だという結論が導かれる。
それから、Worum-willenという術語についても、「これのために」という直訳に基づく解釈が続いた後、より訳し込んだ訳が俎上に載せられる。そして、「究極目的」という訳語の難点が紹介されつつ、「主旨」という訳語の方が適切であることが解説される。
こうした一連の訳語の検討の過程を辿ることで、私たちは、『存在と時間』におけるハイデガー用語の意味を、驚くほどの明晰さで理解できるようになる。ああそうか、そういうことなのか、と目が開かされる。それと同時に、ハイデガーがこれらの術語によって何を狙っているのかが分かるようになるのである。
そしてこの過程は、ハイデガー自身が『存在と時間』のなかで、アリストテレスをはじめとする古典の読解と翻訳を通じて実践していることでもある。古代ギリシア語の訳語の検討によって生まれたハイデガーの現代ドイツ語の訳語を検討する、という本書の営みは、ハイデガーの思考を追体験しながら、「哲学する」ことへと読者を巧みに誘導する実践でもあるのだ。
では、そもそも「哲学する」とはどういうことだろうか。先に少し触れたように、それは少なくとも、物事に対する従来の見方を掘り下げ、その見方を変える、ということを含む。
本書によれば、『存在と時間』はたとえば次のような発想の転換を促している。
〈まず事物が目の前に存在して、それがやがて道具として手許で用いられる〉のではなく、〈さしあたりすでに道具として手許に存在するものが、故障したり役に立たなくなったりすることにおいて、それが目の前に存在する事物となる〉
〈私たちは日常においては固有な存在ではないから、固有な存在に至らなければならない〉のではなく、〈私たちはすでに固有な存在であるからこそ、日常的には私たちは自分自身ではない〉
〈私たちはずっと生きることができない、生き続ける能力がない〉のではなく、〈私たちは死ぬことができてしまう、死ぬ能力がある〉
〈罪を犯したから、その結果として、私たちは責めある存在になる〉のではなく、〈責めある存在でなければ、罪を犯すことは不可能である〉
以上のような発想の転換の内実や、それが意味することについては、ぜひ、本書を読んで確認してみてほしい。ハイデガーの特異な言葉遣いや奇妙な術語、それらを駆使した仕掛けやアイディアを解きほぐしてゆくことで、これまで思ってもいなかった見方が開かれるはずだ。私たち自身の存在について。周囲の事物の存在について。日常性について。自分に固有の生を送ることについて。そして、倫理の根源について。
* * *
総じて本書は、古典を読み解くことの意義、古典を読み解くことで立ち現れてくるものの豊かさを、あらためて私たちに認識させる本だと言える。世界に対する凝り固まった見方や、人間に対する硬直したイメージに対する別の新鮮な見方を、『存在と時間』は自身に先立つ古典の読解を通してかたちづくる。そして私たちは、『存在と時間』という古典を読解する本書を読解することで、そのことを「身をもって」理解できるのである。
それゆえ本書は、『存在と時間』という書物自体に対する見方の転換をもたらしてくれる本だとも言える。『存在と時間』は、しばしばそう受けとめられているような、難解な術語が散りばめられた衒学(げんがく)的な書物などではない。もっと身近で、ユニークなものだ。
『存在と時間』は人間の存在について探究するものでありながら、そこには「人間」という言葉も、それから「心」や「意識」といった言葉も登場しない。それはなぜだろうか。
この書物においてハイデガーは、ギリシア語の「アレーテー」を定訳の「Wahrheit(真理)」でなく、敢えて「Unverborgenheit(隠れなさ)」と訳し、「ロゴス」も、定訳の「Logik(論理)」や「Vernunft(理性)」などではなく、「Rede(語り)」と訳している。なぜハイデガーは、そうした素朴でぎこちない訳語を選び取るのだろうか。
――本書『ハイデガー『存在と時間』を解き明かす』は、そうした種々の疑問に対する答えを粘り強く探りながら、古典を読み解く現場、そして哲学する現場へと、私たちを自然に導いてくれるのである。
プロフィール
古田 徹也 (ふるた・てつや)
1979年、熊本県生まれ。東京大学文学部卒業、同大大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。新潟大学准教授、専修大学准教授を経て現在、東京大学准教授。「言語」「心」「行為」の各概念を手掛かりに、英語圏・ドイツ語圏の現代哲学・倫理学を専攻する。ウィトゲンシュタインの『講義・数学の基礎編』と『ラスト・ライティングス』を全訳(いずれも講談社、前者は大谷弘氏との共訳)。著書に『はじめてのウィトゲンシュタイン』(NHKブックス)、『それは私がしたことなのか――行為の哲学入門』(新曜社)、『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ)、『不道徳的倫理学講義――人生にとって運とは何か』(ちくま新書)、『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』(角川選書)など、訳書に上記『ラスト・ライティングス』など、監訳書に『現代倫理学基本論文集Ⅲ 規範倫理学篇②』(大庭健編、勁草書房)がある。
関連書籍
関連コンテンツ

