
【著者インタビュー】世界の法はなぜ戦争を防げないのか?――忘れられた日本人・安達峰一郎から考える「戦争と平和」
国際連盟・常設国際司法裁判所の創設、不戦条約の発効まで、第一次世界後の国際秩序の構築に深く関わりながら、なぜ日本は戦争の道へと邁進してしまったのか。ロシアによる戦後国際秩序への挑戦が続く中で、今こそ日本が陥った当時のジレンマを仔細に検討する――。そんな問いから上梓された近刊『帝国日本と不戦条約』の中では、知られざる日本人・安達峰一郎という人物が象徴的に語られています。安達峰一郎とはいったい何者か? 著者の国際法学者・柳原正治先生にお話を伺いました。
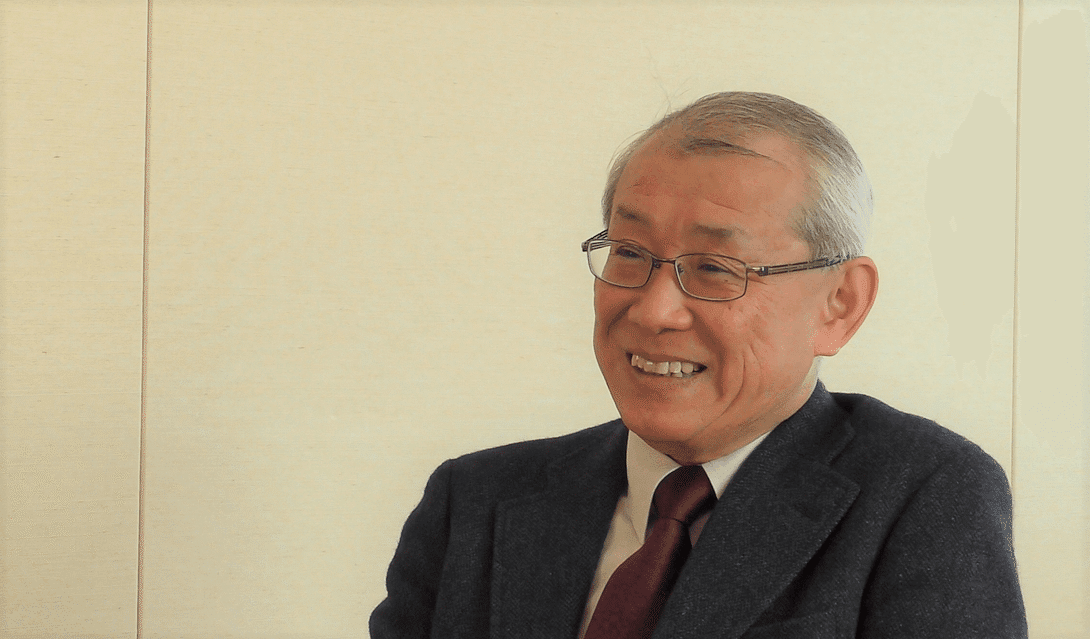
――3月18日、ウクライナ軍事侵攻をめぐって、ロシア軍がウクライナの占拠地から違法に子どもを連れ去った戦争犯罪の容疑の責任があるとして、国際刑事裁判所(ICC)がプーチン大統領に対して逮捕状を出して話題になりました。一方で、昨年から続くこの軍事侵攻では、国際法秩序の限界も囁かれます。先生の今回の著書『帝国日本と不戦条約』では、戦間期に生きた安達峰一郎という人物を軸に、当時の国際法秩序がどのように形成されたか、そして日本がそこから逸脱するまでにどのような葛藤があったかを論じられていますね。まず、安達峰一郎をよく知らない我々のために、簡単にご紹介をいただけますか。
柳原 安達は明治になってすぐの1869(明治2)年に山形県に生まれ、日本が国際連盟からの脱退通告をした後の1934年に亡くなりました。まさに日本が近代化の道を歩んだのちに戦争に走っていく、その時代をずっと生きた人です。
彼は外交官・裁判官・国際法学者という三つの側面を持つ、非常に多彩な人でした。大学を卒業後すぐに外務省に入り、その後40年近くにわたって外務官僚・外交官を務めたのですが、彼に特徴的なのは在外勤務がとても長いことでした。イタリア、フランス、メキシコ、ベルギーなどを渡り歩き、当時としては異色のキャリアだと思います。
そして第一次世界大戦後、国際連盟とともに発足した常設国際司法裁判所のアジア初の所長に就任しています。1931年のことです。同時に、学術論文は残していないものの、国際法学者としても、世界の著名な法学者を集めた万国国際法学会の、日本人として最初の正会員となり、世界の国際法学者に認められていました。
――著書には若いころから熱心に国際法の勉強をしていたとあります。なぜ安達は国際法に関心を見いだしたのでしょう?
柳原 よく言われるのは1886年のノルマントン号事件ですよね。これは横浜から神戸に航行していた英国貨物船が和歌山の沖合で座礁沈没し、イギリス人などの乗組員は全員救助されたのに日本人乗客とインド人水夫は救助されず溺死しました。ところが領事裁判権に基づく海難審判ではイギリス人船長は無罪とされたのです。当時、この判決に世論は沸騰しました。
もちろん明治政府も黙っていたわけではありません。不平等条約を改正することが政府の外交政策の基本であり、そのためには国際法を知っていなければならない、さらに言えば欧米並みの「一等国」にならなければならない、というのが政府の基本政策でした。若かりし安達が生きたのはそういう時代です。彼が若い頃に書いた書簡には、国内法を勉強しようとする人は多いが、国際法を勉強して国家に尽くそうとする人は多くない、自分はそれを目指すんだ、と書いています。
外交官となって最初に赴任したのがイタリアでしたが、当時は船舶での移動ですから、東南アジアを通過していくわけです。すると、寄港する土地土地が欧米の植民地になっている。アジアの人々が欧米諸国によって虐げられている様子を間近で見て、日本は一等国にならなければならない、という決意を、日本に残った妻・鏡子(かねこ)に宛てた書簡にしたためています。
――安達は非常に筆まめだったとか。
柳原 そうなんです。まとまった本や論文はないのですが、書いた手紙やもらった手紙はたくさん残っています。これらの書簡が研究の役に立ちました。書簡を見ると、彼が非常に広い交友関係を持っていることがわかります。欧州の学者、政治家だけでなく、アメリカの学者や政治家とのネットワークもあることが、書簡を見るとよくわかります。
国際連盟で活躍し、長年ヨーロッパに住んでいたことからその雰囲気を肌身で知っていて、また裁判官として実際の紛争の解決にも尽くしている。欧米の人々がどう考えて、世界はどう動いていこうとしているのかについて、ヒューマンネットワークの広さを元にした鋭敏な国際感覚、豊富な情報を持っていたと言えます。
国家自存と平和構築の狭間での苦悩
――そんな安達峰一郎という人物に、先生が興味を持たれたのはなぜでしょうか。
柳原 19世紀末から20世紀初頭にかけて日本は不平等条約の改正を達成し、日清・日露戦争ののち、欧米に並び立つ「一等国」になりました。その後第一次世界大戦を経て、日本は国際連盟や不戦条約をはじめとする新しい集団安全保障体制の構築に密接に関わり、国際会議の中で然るべき地位を占めるようになっていった最中、「戦争」にひた走っていきます。
そうした近代日本が辿った道を、安達は局面局面で体験しています。安達は戦間期にパリ講和会議の委員を務め、国際連盟の発足にも関わっていて、満州事変が起きた当時は常設国際司法裁判所の所長を務めていました。近代日本のたどった道は、そのまま安達が辿った道でもあるのです。その中に彼自身の大きな葛藤があった。国際平和を達成するという目的と、昭和初期の日本がそうした方向に進んでいないのではないかという疑念との間のギャップの中で非常に苦悩していたのです。近代日本が歩んだ道筋を、安達が書き残したものを見ながらたどっていくと、近代日本自身の葛藤がよく見える。これが、私が安達に関心を持った最大の理由ですね。
――安達が当時稀有な立ち位置にいた日本人だったということがよくわかります。何か彼の「葛藤」が具体的にわかる逸話がありますか。
柳原 ひとつ挙げるとすれば、やはり満州事変との関係でしょうか。満州事変は1931年9月に勃発しました。安達は同年1月から常設国際司法裁判所の所長に就任しているので、外務省からは離れています。この時に、中国側は満州事変を連盟理事会だけでなく、常設国際司法裁判所にもかけて議論したいという意向を持っていました。実際にフランスやスペインはこれに賛成していたようですが、安達はその情報をいち早くキャッチして、日本の在オランダ公使にその動きを伝え、同時にこの問題が常設国際司法裁判所に付託されて議論されると、おそらく日本は不利な立場に置かれるということを内密に伝えています。日本外務省としてはそうなっては困るので、色々画策をしていくことになります。
安達は、裁判官ですから本当は中立な立場でなければなりません。しかし、日本の国益を考えると、常設国際司法裁判所に付託されるという状況にはなってほしくない。それはある意味で、彼の置かれた状況の厳しさを如実に示している逸話です。ずっと職業外交官で、日本を一等国にするために国際法を熱心に勉強し、国際法に則った外交をすべきだと主張してきた一方で、日本の国益を守らなければならない、という思いがある。この二つのせめぎ合いの中で、彼自身は葛藤していたのだと思います。
国際法は万能薬ではないけれど
――『帝国日本と不戦条約』は、そんな安達のどのような側面に注目した本でしょうか。
柳原 1924年のジュネーブ議定書を経て、1928年のパリ不戦条約が発効する中で、安達は「戦争をしてはいけない」という考え方を強く支持するようになっていきます。世界はもはや戦争によって紛争を解決する時代ではなくなったんだ、国家間で紛争が起きた場合には国際裁判によって解決する時代が訪れているんだ、というようにです。そして、日本には必ずしもそうした価値観が伝わっていないのではないかという危惧も持っていました。1930年に日本に帰国して、そうした危機感を多くの講演で訴えています。彼としては世界の雰囲気が変わっていること、裁判によって国際平和を達成する時代がほぼ訪れているという時代認識をなんとか伝えたかったのでしょう。
しかしそんな最中に満州事変が起きてしまう。安達は1934年に亡くなっているので、日華事変や大東亜戦争を経験していませんが、もし経験していれば、彼の嘆きはいかばかりだったかと思います。
もちろん満州事変も「日本がこんなことを犯すのか」という衝撃があったと思います。正確に言えば、満州事変は「戦争」ではなく「事変」と捉えられており、その辺りは非常に微妙なところで、戦争と事変がいかに違うかということは、拙書からよく読み取っていただきたいのですが、いずれにしても武力紛争が起きている。そこから安達の葛藤が深まっていくわけですね。戦争はなくすべきだという時代が来つつあるのに、日本はこんなことをやっている。この葛藤の中で、なんとか日本を良い方向にもっていきたいと、彼なりの尽力をしています。明治から大正を経て、昭和初期に至るまでに帝国日本がたどった道を、安達峰一郎という人物を「象徴」と位置づけて問いなおしてみたい、と思って書いたのが今回の本です。
――戦間期に日本が味わった苦い経験を通して、我々は何を学べるでしょうか?
柳原 国際秩序を考えるときに、大きくくくれば、二つの捉え方があると思います。ひとつは理想主義の考え方、もうひとつは現実主義の考え方です。武力を持たずひたすら国際平和を希求すべきだ、という考え方と、現実として武力闘争は起きているわけだから、国際社会は結局武力によって決まっているのではないかという捉え方です。日本は満州事変以後、現実主義の考え方に極端に走っていきました。私は、安達は理想主義と現実主義の中間点を目指していたと思うのです。そのために、今ある国際法が不十分であれば、改善したり拡張したりしていく永続的な努力が必要なんだと考えていました。そうした姿勢は、20世紀の著名な国際法学者であるブライアリーの『国際法』という著書の内容とも共通します。国際法はキマイラ、神話上の存在ではなく、現に存在しているが、その一方で国際法はけっして万能薬ではないという考えです。
ロシアのウクライナ侵攻によって、国際法は何の役にも立っていないのではないか、と思っている一般の方も多いかと思います。でも、ではどうすればいいのでしょうか。ひたすら平和を祈念するのでもなく、武力のみに頼るのでもなく、その中間点を目指すというのが、まさに安達が戦間期に目指した道だったと思います。実際に彼は、亡くなる半年ほど前の書きかけの書簡で、自分は国際裁判の改善に対するプランを練っていると書いています。満州事変が起きても有効な国際裁判制度を作れないかと、あきらめずに考えていた。
それは茨の道かもしれません。武力によってではなく平和的に国際法の改善・拡張を実現することはたいへん難しい。しかし、状況は変わっていくわけですから、それに適応する国際法もあってしかるべきでしょう。その構築を平和的に実現することを目指すことが重要だと思いますし、安達はそういうことをずっと言い続けていました。そうした諦めない姿勢というのは、今の時代には一段と必要なのではないかと思います。諦めてしまったらその先はなにもありませんから。
柳原正治(やなぎはら・まさはる)
1952年富山県生まれ。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。九州大学名誉教授、放送大学特任栄誉教授。著書に『人と思想 グロティウス』(清水書院)、『国際法』『法学入門』(放送大学教育振興会)、共編著に『安達峰一郎――日本の外交官から世界の外交官へ』『国際法からみた日本の領土』(東京大学出版会)などがある。

