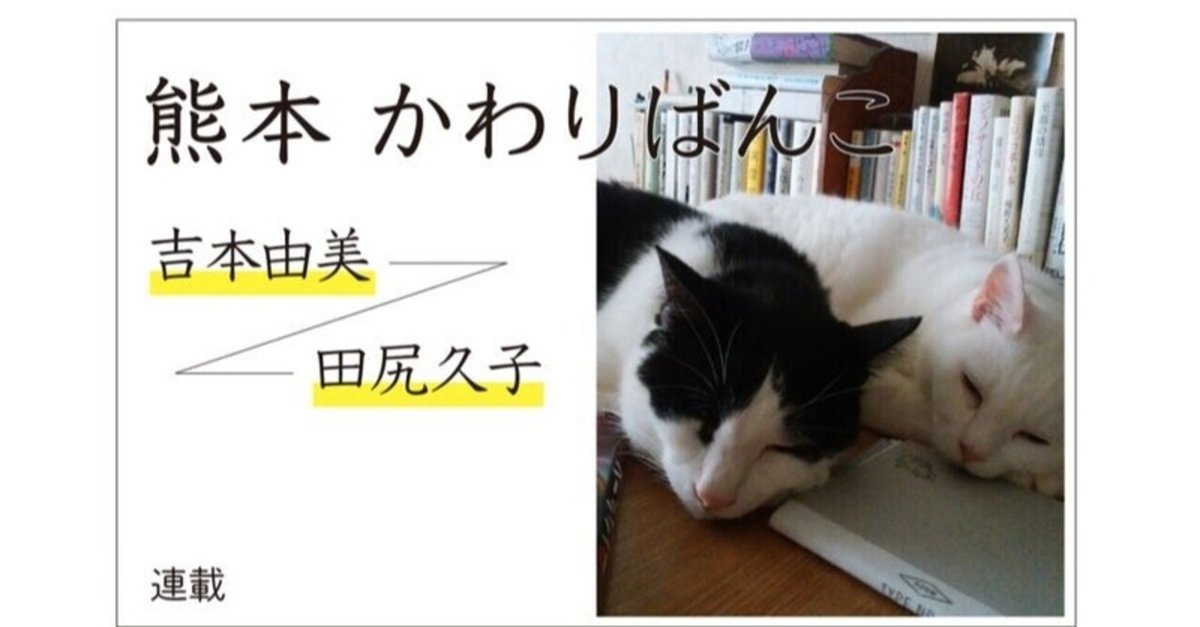
オリーブ少女ではなかった私――「熊本 かわりばんこ #02〔忘れがたい春と募金箱のこと〕」田尻久子
長年過ごした東京を離れ故郷・熊本に暮らしの場を移した吉本由美さんと、熊本市内で書店&雑貨カフェを営む田尻久子さん。
本と映画、そして猫が大好きなふたりが、熊本暮らしの手ざわりを「かわりばんこ」に綴ります。 ※#01から読む方はこちらです。
忘れがたい春と募金箱のこと
1980年代はじめ、私が中学生の頃に『オリーブ』が創刊された。若い方は知らない人もいるだろうが、私と同世代でこの雑誌のことを知らない人はあまりいない。世の中にオリーブ少女を生み出したファッション誌だ。田舎の貧乏な中学生にとってファッション誌は興味の対象ではなかったが、高校に通うようになると、同じ制服を着ているはずなのにまわりとはどこか違う雰囲気を醸し出す女の子が、身の回りでは見たことのないような雑貨や着飾った少女たちの写真が載っている『オリーブ』を愛読していた。スタイリストとして吉本由美さんの名前が掲載されていることに気付くのは、大人になってからだ。当時はまだ、雑誌の誌面をつくりあげる人たちにまで気が回ることはなかった。
私はオリーブ少女ではなかった。平日は学校の制服、休日はバイト先の制服、あとはよれよれの部屋着で済ませる高校生だった。洋服を買う余裕はなかったし、そもそもファッション誌には今も昔もあまり興味がない。高校生の頃のバイト代は、ファッション誌を買うよりも1冊の文庫本を、あるいは映画を1本でも多く見ることに費やした。
吉本さんのことを知っていたのは熊本出身だからだ。今はどうだか知らないが、私が若かった頃、「熊本」という街は「わさもん」が多いことで有名だった。「わさもん」とは熊本弁で「新しもの好き」という意味だ。セレクトショップが多く、熊本で売れると他でも流行るとか言われていて、先行して商品が販売されることもあったと聞く。そんな街で暮らしていると、「スタイリストの吉本さんは熊本出身」という情報はどこからともなくやってくる。その「吉本さん」が熊本に暮らすことになったらしい、という情報を大橋歩さんが雑誌に書かれていて知った。もちろん読んだときは、いつか会うことになるとは思いもしない。でも、縁はつながりお会いする日が来た。吉本さんにはじめて会った年がいつだったかを忘れることはない。何もかも忘れてしまわない限り。2011年の春は忘れがたい春だったから。
今年は早いうちから桜が咲いた。コロナ禍がはじまってからにぎやかな花見の光景をほとんど見ていない。私も、家の窓から見える公園の桜をひっそり楽しむばかり。桜より先に咲く木蓮も楽しんだ。先だって公園の遊具が新しくなったので、いつ見ても子どもたちでにぎわっている。近くに大きな湖があるので、にぎにぎしい鳥のさえずりも聞こえる。今は桜が散り、むせかえるような新緑が公園をいろどっていて、朝起きてすぐに眺めては、ほおっと息をついている。

桜の季節になると地震のことを思い出す。5年前の熊本地震は4月に起きた。連鎖するように、10年前の東日本大震災のことも思い出す。3月11日と4月16日、その間に熊本の桜は満開になる。通勤路の桜並木を横目で見ながら、人間がどんなに動揺していても桜は咲くし新芽は伸びると何度も思った。それが自分を安心させるためだったのかどうか、よくわからない。
2011年の3月11日、私は営んでいる店で写真家の友人が東京から来るのを待ちわびていた。テレビもラジオもないので、大きな地震が発生したことにお客さんから言われるまで気が付かなかった。東京もかなり揺れたと聞くが来ることはできるのだろうか、来られるとして東京を離れて大丈夫なのだろうかと心配になった。友人は地震の混乱をなんとか逃れ熊本に着いたが、徐々に被害の大きさが伝わり、原発事故まで起きるとは……と私たちは呆然とした。
滞在中、彼女の東京の友人から、しばらく熊本にいたほうがいいかもと連絡が来ていた。彼女は悩みつつも仕事もあるしと、予定通り東京へと帰った。東京を離れていることで増す不安もあっただろう。私はその不安を支えることができなかったような気がするし、自身が災害を体験したあとだったら、かける言葉も違ったのではないかと今となっては思う。彼女はのちに被災地を訪れ、がれきの中で白と黒のつがいの鳩に出会い、写真に収めた。
それから5年後、熊本地震が発生した直後からしばらくは、毎日のようにその友人が電話をくれた。「大丈夫?」と聞いてくれ、それから少しだけとりとめのない話をした。彼女の声を聞くといつも安心した。

東日本大震災の直後、「自粛」という言葉が飛び交いイベントの多くが中止・延期になったことに、どこか釈然としなかった。世間で言うところの「自粛」とは、本当に東北の人々のためになるのだろうか、という疑問が頭をもたげた。同調圧力に従っているだけなのではないか。「自粛」をうながさなくとも、被害の状況を知れば誰もが心を痛めるし、何かできることはないかと問うものだ。東北から遠く離れた地に住む私たちは、被害にあった人々に心を寄せるために、むしろしっかりといつも通りの暮らしをせねばならないのではないか。催しの中で支援を訴えかけるという方法もあるのではないか。「自粛」よりもやるべきことがある気がしてならなかった。
ちょうどその頃、普段はカリフォルニアに住んでいる詩人の伊藤比呂美さんが熊本にいた。伊藤さんが言い出したのか、熊本文学隊(伊藤さんが隊長で、私が営む橙書店が事務局をやっている)の誰かが言い出したのか、私が言い出したのか、記憶はおぼろで思い出せないのだが、チャリティー朗読会をしようという話が出た。とはいえ、伊藤さんがカリフォルニアに帰る日まであと1週間もなく、人を集める自信は正直なところあまりなかった。当時は今ほどSNSがさかんではなく、伊藤さんも「人、来るかしら?」と不安げだった。普段のイベントも、たかが定員30名を集めるのにいつも四苦八苦する。しかし、どこに向けて腹を立てているのかもわからないまま憤っていた私は、強固に「やりましょう」と伊藤さんにお願いをした。完全チャリティーで募金さえしてくれたら入場無料、出入り自由。伊藤さんはノーギャラになるが、二つ返事で引き受けてくださった。最初から最後まで朗読だけでやるからみんな辛いかもよ、と。
朗読会は20日と決め、告知をはじめたのが17日。それでも、地元の新聞社にお願いをしたらすぐに告知を出してくださった。私はSNSを一切やっていなかったのでまずは店のホームページに告知を出し、あとは電話をかけたり、店内でお客さんに直接声をかけたり。その先は人づてを頼った。
普段は予約してもらうので来場者数はおおむね予測がつくが、このときは予測不能だった。満員になる可能性もあれば、面と向かって伊藤さんの朗読を聞くのがいたたまれないくらい(伊藤さんの朗読は迫力がある)お客さんが少ない可能性もある。少なくとも、参加するお客さんは伊藤さんの朗読で少し元気が出るはずだからまあいいか、と開き直り当日を待った。
普段のイベントと違って打ち上げもやらないし、受付作業もないから、当日やることと言えば、客席をつくることくらい。今の場所に引っ越す前は、喫茶店と書店は隣接する別の店舗を借りていて、人ひとり通れるくらいの穴を壁に開けて行き来していた。朗読会は書店側でやるので、まずは書店の真ん中に置いているテーブルを店の外に出し、募金箱や伊藤さんの本を並べる。他の動かせる什器は喫茶店側に移動し、少なめに椅子を並べ様子を見ることにした。
伊藤さんは「勝手知ったる場所」だからぎりぎりにしか来ないだろうし、あとはお客さんが来るのを待つだけ、受付がないって手持ち無沙汰だな、とのんきに構えていたら予想だにしない状況になった。開演時間が近づくとあれよあれよと人が集まってきたのだ。椅子を並べると30人くらいしか入らない空間なのだが、すでに定員を超えているように見えたので、とりあえず店の前の通路に並んでもらった。
熊本地震のあと店を引っ越したのだが、旧店舗は路地裏にあった。古い長屋が向かい合って連なっている場所で、店の前は人がやっとすれ違えるくらいの狭いアーケードになっている。パリのパサージュというよりも、戦後の闇市といった風情の私道だ。もたもたして道をふさぎ続けると近所のお店に迷惑をかけてしまう。急いで後ろの席をすべて取り払い、前の方だけ椅子を残し、立ち見のスペースをつくった。その間も人は増え続ける。通路にあふれんばかりの人がいるのを見ながら、これじゃ、ほんとに戦後の闇市みたい……と思った。
「椅子はご年配の方や、前が見えづらい人に譲ってくださいね」と声をかけながらお客さんを誘導したら、遠慮して誰も椅子に座らず譲りあっている。こんなときだから、いつにも増して他人を思いやる気持ちになるのだろうか。余計なことを言ったかもしれない、と思いながら、適当な人を見つけて座ってもらう。書店の二階には小部屋があって、上からは下がのぞけるし声も聞こえるので、気兼ねなく聞けるように小さいお子さん連れは二階に上がってもらった。常連さんの中には、こっちで聞くからいいよと喫茶店側に入ってくる人もいる。店内はほぼ満杯になったが、相変わらず伊藤さんの正面辺りの席だけは空いている。そうこうしていたら伊藤さんが登場した。お客さんに取り囲まれても、伊藤さんの迫力は負けることはない。今日は朗読だけで通すから覚悟してくださいね、お帰りの際はみなさん募金をお願いします、などとまずは観客をなごませる。
突然の告知だったし、雨も降る足元の悪い日だったので、遅れてくる人もちらほらいた。今日は途中からだって、終わり間際だって入ってもらう覚悟ではじめたので、たとえ相手がひるんでも「どうぞどうぞ」と引っ張り込む。幸い、書店と喫茶店は別の店のように見えて中でつながっているから、壁の穴から入ってもらえば演者前の特等席に案内することができる。
朗読がはじまる寸前、小柄の女性が入って来た。伊藤さんの前に置いた小さな椅子がちょうど空いていたので勧めると座ってくださった。見かけない人なのに、ただ者ではなさそうな雰囲気が気になったその人が吉本由美さんだったが、そのときは気付かない。

伊藤さんのイベントは普段は主にトークで楽しんでもらうのだが、今回は挨拶もそこそこ、店からあふれんばかりの人に囲まれ朗読がはじまった。題目は『方丈記』。朗読の合間には、子どもたちの声がときおり二階から降ってくる。通り沿いは大きなガラス窓なのだが、人で埋め尽くされているので外からは中の様子がわからず、アーケードを歩いている人がいぶかしげに通って行く。
朗読会が終わると伊藤さんは「いくらある? 募金箱早く開けようよ」とせかしてきた。「もうちょっと片付くまで待ってくださいよー」と言っても、開けよう開けようと気になってしょうがないようだったので、開けてみると小銭から一万円札までぎゅうぎゅうに入っていた。みんなで手分けして数えると予想以上にかなりの額が入っていて、歓声があがる。久しぶりに笑顔の人たちを見た。
実は、その日いちばん印象深い記憶は朗読そのものではなく(惜しまれるが、私は当日対応にあたふたしていてまともに聞けなかった)、名前もわからない通りすがりの男性のことだ。しかも直接見たわけではなく、書店の中で朗読を聞いていたお客さんから伝え聞いた話。
募金箱は朗読会がはじまってからも外に出したテーブルに置きっぱなしだった。来場者の方には帰り際に寄付を呼びかけるつもりだったが、はじまる前に入れてくださった方もいて、すでにお金は入っていた。「誰もいないところに置いておいたらあぶないでしょう」と心配する人もいたが、都合で最後まで聞けない人が帰りに入れてくださるかもしれないし、持って行く人などいない気がした。
朗読会中に、背広を着た、いかにもサラリーマンといった風情の男性が貼り紙にじっと見入っていたという。入り口の扉には、「東日本大震災のチャリティー朗読会で、寄付をしてくださればご自由に入場できます」といった趣旨を書いた紙を貼っておいた。扉の近くに立っていて男性の気配を察したお客さんは、募金箱が置いてあるのが気になってちらちらと見ていたのだとおっしゃった。男性は、貼り紙の文章を読み終わったあと、しゃがみ込んでカバンから財布を取り出し一万円札を募金箱に入れて立ち去ったそうだ。
この日のことを思い出そうとすると、その人の立ち去る後ろ姿がまず見える。私の想像の中の姿だが。

続きは書籍をお読みください。
プロフィール
田尻久子(たじり・ひさこ)
1969年、熊本市生まれ。「橙書店 オレンジ」店主。会社勤めを経て2001年、熊本市内に雑貨と喫茶の店「orange」を開業。08年、隣の空き店舗を借り増しして「橙書店」を開く。16年より、渡辺京二氏の呼びかけで創刊した文芸誌『アルテリ』(年2回刊)の発行・責任編集をつとめ、同誌をはじめ各紙誌に文章を寄せている。17年、第39回サントリー地域文化賞受賞。著書に『猫はしっぽでしゃべる』(ナナロク社)、『みぎわに立って』(里山社)、『橙書店にて』(20年、熊日出版文化賞/晶文社)がある。
吉本由美(よしもと・ゆみ)
1948年、熊本市生まれ。文筆家。インテリア・スタイリストとして「アンアン」「クロワッサン」「オリーブ」などで活躍後、執筆活動に専念。著書に『吉本由美〔一人暮らし術〕ネコはいいなア』(晶文社)、『じぶんのスタイル』『かっこよく年をとりたい』(共に筑摩書房)、『列車三昧 日本のはしっこへ行ってみた』(講談社+α文庫)、『みちくさの名前。~雑草図鑑』(NHK出版)、『東京するめクラブ 地球のはぐれ方』(村上春樹、都築響一両氏との共著/文春文庫)など多数。

