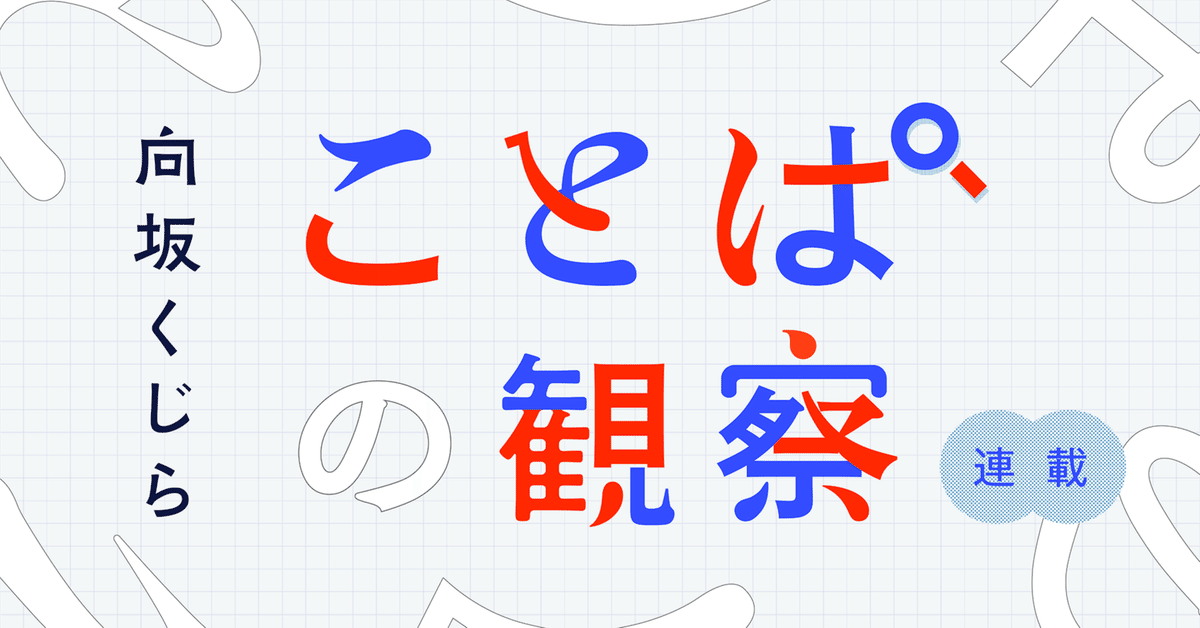
たくさんの言葉を、ほんとうは見過ごしながら暮らしている。――「ことぱの観察 #01〔友だち〕」向坂くじら
詩人として、国語専門塾の代表として、数々の活動で注目をあびる向坂くじらさん。この連載では、自身の考える言葉の定義を「ことぱ」と名付け、さまざまな「ことぱ」を観察していきます。
友だち
「いろんな言葉を定義していく、みたいなのはどうでしょう」
編集者さんとの打ち合わせで連載のテーマをそう提案してもらって、真っ先に思い浮かんだのは、友だちとの会話によく出てくるひと言だった。たとえば、わたしが愚痴を聞いてもらっているとき。
「もうほんとに最悪。終わりです」
「ブチギレやんか」
「ブチギレとかではないのよ」
「ブチギレてはいるでしょ」
「そういうんじゃないのよ」
「んー。語義やね」
この「語義やね」というのが、わたしと友だちの間では定番化しているセリフ、というか会話の落としどころで、話していてどうもやりとりが立ちゆかなくなったときに使う。この場合は、わたしはあくまでまだ「ブチギレ」てはいないと思っているものの、友だちから見るととてもそうは見えないらしい。そこに齟齬が生まれる。
この齟齬の解釈として、まず「友だちによる見立てが誤っている」という可能性がある。友だちはあくまで他者であって、わたしの感情を推しはかることには限界があり、「ブチギレ」ではないものを「ブチギレ」と誤認している、という考え。次に、「わたし自身の見立てが誤っている」こともありえるだろう。さっきはああ言ったが、とはいえ当の本人がいちばん自分の感情に気がついていないなんてことはよくあるもの。ましてわたしは「ブチギレ」ているらしいのだから、自分がどういう状態にあるのか冷静には判別できていないかもしれない。そう思うと、「友だちのほうがわたしの感情を正確に見抜いている」と言うこともできそうだ。
そして、そのどちらでもない第三の解釈として、「わたしたちはそれぞれ異なる事象を名指して『ブチギレ』と呼んでいる」というのがある。そして、いまのところ、つまり「語義やね」と言うときには、それを採用している。仮に、「ブチギレ」と「キレ」と「まったくの平常心」とのあいだになんらか線引きがあるとして、その線を引くポイントが互いに違うのだろう、ということだ。事象を見る目線による齟齬であるというよりむしろ、言葉を見る目線による齟齬である、とでも言おうか。そうなってしまうともう、これ以上わたしが「ブチギレ」ているかどうかを話しあってもしかたない。わたしが「その状態」にあることはなんと呼ぼうと変わらない以上、それが「ブチギレ」であるか「キレ」であるかを互いに話しあうことに、そこまでの値打ちを感じない。
なお、このときの愚痴は別の友だちについてで、わたしはこのあとその人と大げんかして二年ほど絶縁した。確かに、「ブチギレ」ていたのかもしれない。けれどそののち、わたしから謝って仲直りした。これはわたしにはめずらしいことで、やっぱり、「ブチギレ」とは質の違うものだったのかもしれない。ほら、ばかばかしくなってきたことだろう。どっちでもいいわ、と思うだろう。
「どんな意味でその言葉を使っているか」を語ろうとすると、たいてい会話は袋小路に入ってしまう。ふしぎなもので、ばかばかしいと思っていながら、なぜか喧嘩腰になることもある。だから、「語義やね」と言って一旦検討にカタをつけることで、わたしと友だちとは会話を先に進める。お互い、細かな理屈のズレが気になるタチだとわかっているから、なおさら。
そんなふうにして、たくさんの言葉を、ほんとうは見過ごしながら暮らしている。わかったような顔をして、実際のところそこまでの不自由もなく、なんとなく暮らせてしまっている。けれどもこの連載では、あえてその尻尾をつかまえて定義をしてやろうというのだ。果たしてそんなこと、できるのだろうか。
ところで、ふたりいるLINEスタンプが送れない。
なんのことだかわかるだろうか。スタンプ自体は、わたしもよく使う。たいていは絵で、ベーシックなのはなにかキャラクターがうれしい顔をしたり悲しい顔をしたり、とにかくなんらかの感情を明らかにしている。それを相手に送ることで、送り手である自分もまたそれに近い感情であることを示すのである。また動作が描かれているのもあって、今度はキャラクターが踊っていたり走っていたりする。それが案外便利で、送るタイミングによって状況に合わせた意味になるからおもしろい。
その中に、ふたり描かれているものがある。キャラクターどうしがハイタッチをしていたり、殴りあいをしていたりする。これがちょっと苦手である。そういう、ふたりが対等でおおよそ同じ動作をしているものならまだいいが、片方が殴っていて片方が殴られている、片方が怒っていて片方が怒られている、というような、立場の異なるふたりが出てくるものはいっそう送りづらい。まず、どちらに感情移入すればよいのかわからない。もしもこちらのイメージの中ではどちらがわたしでどちらが相手か決まっていたとしても、それを誤解されそうなのも怖い。そしてなにより、わたしの一方的な発語によって、相手のリアクションまでも規定してしまうことが怖い。
仮に怒りの気持ちを相手に向かって表明するとして、本来相手はそれに対して自由にリアクションすることができるはずだ。反省することもできるし、無視することもできるし、逆ギレすることもできる。もっと高度なところでいけば、「反省しているような顔をしてちょっと当てこすりを言う」とか、「反抗的な態度をとっているけれどもかわいげを見せる」だとか、そんなこともできる。けれども「片方が怒っていて片方が怒られている」スタンプを送るとき、そこにはすでに相手とおぼしきキャラクターが写っていて、わたしとおぼしきキャラクターに向かってぺこぺこと頭を下げている。それは、あまりに送る側の勝手ではなかろうか。
同様に、ハグやらキッスやらのスタンプも、どうしても送れない。一見、怒る/怒られるとは違って対等な関係ふうだけれど、しかしそんな繊細な接触を、こちらから勝手に成立したものとして送るわけにはいかない、と思えてならない。知人はおろか、結婚してもう三年になるけれど、夫にすら送れない。キッスの気持ちになったときには、投げキッスのスタンプですませる。投げキッスであれば一応はわたしひとりの行為に留まっていて、それを受け取るかどうかというところでは夫の自由がまだ残されているように思えるからである。
そしてそれと同様に、「友だち」という言葉がうまく使えない。
「わたし、あなたと友だちになりたいと思っているんだよねえ」
前述した「語義」の友だちにわたしがそう言ったとき、友だちは腰を抜かしたらしい。
「ちょっと待って、一応確認なんだけど、いまはなんだと思ってる?」
「なんか仲いい、知ってる人」
「マジかあ〜」
少し申し開きをさせてもらいたい。「友だち」という言葉、使うのに、ハードルが高すぎやしないか。まず、ふたりの関係を指す言葉でありながら、多くはなんの約束もなく発せられる。誰かのことを勝手に「恋人」と言うことはないし、もしそういう人がいたとしたら、ちょっと距離を置かれることだろう。その点で、わたしにとっては「恋人」のほうがまだ気やすい。かつそれでいて、「あの人は友だちではない」という線引きもまた確かに存在するように思える。「あの人は知りあいだよ」と言って否定されることはほとんどないと思うけれど、「あの人は友だちだよ」はまだ、否定される可能性を持ってはいないか。わたしだって、まったく親しみを持っていない人から「友だち」と呼ばれたら、一瞬、固まるだろう。その塩梅が怖い。もともと人との距離感を失敗しやすいわたしであるから、つい警戒したくなる。
それで誰かの話をするときには、なんとなく「大学の先輩」とか「詩関係の人」とか、ある程度は客観的な事実であると言い張れそうな表現でごまかしてしまう。そう思うと、「友だち」は事実ではない。たかだか期待、悪ければ思い込みのたぐい。わたしのほうが「友だち」と思っているだけなのに、そう呼んだとたん、相手を勝手にその枠に押しこめることになりそうなのが気に入らない。ちょうど、ふたりいるLINEスタンプのように、気に入らないのだ。
しかし前述の友だちとは、大学を卒業して何年も経つのにだらだらとつるんでいて、もういい加減ほかの呼び方がしっくり来なくなってきてしまった。そろそろいいか、ということで、「友だち」と呼ぶ許可を取ろうと思ったのだった。わたしなりの、「友だち」と呼ぶことに対する誠意だった。
友だちはしばらく、わたしになにを言うか考えていた。
「君、じゃあ、君の言う友だちはなんなのよ」
「あんたくらい仲良かったら、まあ、友だちじゃだめかね」
「だめっつうか、いや、ズレとるよねえ」
「なにがよ」
「多くの人は、もっと全然仲良くないくらいで、友だちって言うんじゃないかね」
「だからすごいなと思うよねえ。みんな早くに仲良くなれるなあと思って」
「いや違うんだよな、語義なんだよな」
また「語義」である。聞けば、わたしが「友だち」と呼ぼうと思う基準は、平均よりずいぶん遠くにあるらしい。そのときのわたしと友だちは、知りあって五年経っていた。それはわたしのジャッジが厳しいというよりは、思い切って「友だち」と呼んでみるか、と重い腰を上げるまでのためらいの距離なのだが、しかし結果ひどく「ズレている」という。語義がズレている、語と語の線引きがズレている。
「じゃあ、ふつう、このぐらいの仲のよさだとなんて呼ぶの」
「親友?」
「げえっ、ちょっとやめてよ」
のけぞるわたし。「友だち」程度でびびっている者にとっては「親友」などほとんど隠語なのであって、いま文字で書いていても恥ずかしい。「なんなん君。もういいよ友だちで。別になんでもいいよ」と、あきれっぱなしの友だち。このようにして半ば無理やり、その人のことを「友だち」と名指す権利を手に入れ、こうして冒頭から堂々と書いているわけだ。ちなみに、途中で出てきた一度絶縁した友だちのことは、向こうから「自分には現状ひとりしか友だちがいない。君である」とヘビーな申し出があったため、さすがに「友だち」と呼んでよかろうと思っている。
「少し前に、亡くなった友だちがいたんですけど」
そんな体たらくのわたしだから、カメラに向かってそう話しながら、喉がちりちりと痛む気がした。なにか、踏んではいけない結界のようなものを踏んでいて、それがわたしの体を灼いているようだった。NHKの取材を受けているときのことだ。朝のニュースでわたしの活動が取り上げられることになり、話題はわたしの書いている詩のことに及んだ。
そのとき紹介されたのは、友だちに死なれることについて書いた詩だった。
ところが
祝日に訃報がやってきて
それからはわたし
ひとりぶんにも少し 欠けてしまった
左肩のあたりが空いてすうすう痛む
竜巻のような電話をする友だちだった
唐突で 肝心なところになるとよく聞こえなくて
いつも向こうの方が早く眠った
ここで書いているのは特定の誰かのことではなく、生きているものも死んでいるものも含めた何人かの知人を重ねあわせてできた架空の人物のようなものだったが、しかしこの詩を書いたきっかけには、たしかに亡くなった彼女のことがあった。それで、取材ではやむなく彼女について語ることになった。
彼女が亡くなった直後には、日記に「会ったことある人が死んでしまった」と書いた。「友だち」と書くことも、それに「亡くなった」と書くことも、いやだった。死なれたあとのもはやなにもできない自分が、ともすると見せかけだけの敬意を彼女に払いたがるのが自分でわかって、その浅ましさがいやだった。それに、彼女はわたしからするとよくわからない存在で、わたしたちふたりというのもちょっと微妙な関係だった。同い年で、ふたりとも詩人だった。詩のイベントで何回か一緒になったことがあるけれど、ふたりで会ったことはない。共通の知り合いはたくさんいるのに、わたしたちはなぜかそこまで仲良くならず、せいぜいSNSでときどきいいねが来るくらいの仲だった。
その彼女から、一回だけ長いメッセージが届いたことがある。それは、わたしの公開したエッセイに対する感想で、しかも、酷評だった。「正直私はあなたが苦手なので」という告白からはじまり、そこから長々と、わたしの書く文章やふるまいは所詮「大人”らしさ”」にすぎない、見ていてつらくなる、と述べる。そのくせ読み進めるうち、「勝手に大事に思っているので、勝手に心配になって、勝手に苦手になってメッセージしました」と言い出す。わたしにはこのメッセージが、うれしかった。「友だち」とひと言呼ぶにもためらうわたしにとっては、彼女のこの、きっとわたしによく似たためらいがちの口調が、それでいて自分でもどうにもならなかったような率直さが、つんと沁みるのだった。これほどに誰かに正直になってもらえることが、人生でどれほどあるだろうか。いま読み返しても、やっぱりうれしく思う。けれども、メッセージの最後の部分だけは、いまとなっては承服しかねる。
「きっと10年後もお互い続けていられると良いと思っています。その頃にはなんか、漸く、おしゃれで大人なイタリアンバルとか知ってて、一緒に行けたらうれしいです。でも、大好きだよー」
わたしも同じ気持ちでいたから、これがどうしても悔しい。
「その友だちが亡くなったことがあって、この詩を書いたというのはありますね」
何度もくりかえし、そんなふうに話す。カメラの眼はどこまでも黒い。インタビューというのは妙なもので、たずねられて答えるたび、だんだんずっと同じことを話している気分になってくる。だから実際はそう何度も言ったわけではないかもしれないけれど、気持ちの上では、わたしは彼女のことを、何度も、何度も、「友だち」と呼んだ。
インタビュアーにわかりづらくならないように、と、気をつかった部分もある。「会ったことある人が、あっ、といってもたぶん外から見たら友だちみたいなもので、しかしわたしにとって勝手に友だちと呼んでしまうのは怖いことなので……」なんて説明するのが面倒だったから、というのもある。それはまさに、わたしの日ごろ嫌っているあの大ざっぱな気配りによるものだったけれど、しかしわたしの唇がそのことを発するたび、濡れた土が踏みしめられるように、彼女が友だちになっていく、と思った。「友だち」という言葉の持つ、あるいはふたりいるLINEスタンプの持つ、あの勝手さによって。やい、ざまあみろ、と思う。わたし、あなたのことをさんざん、「友だち」と呼んでやった。あなたがどれほどにわたしのことを嫌いでも、あなたはもういないから、わたしのそのような勝手を、もう押しとどめることができない。やあ、ざまあみろよ。
それはやっぱり、「友だち」という言葉の持つ、強すぎるほどの効力によるものだった。
誰かに向かって「友だち」と言うとき、それは先に述べた期待や思い込みにはとどまらない。発話されてしまったが最後、「友だち」という言葉そのものが、呼びかけとして機能するのではなかろうか。「恋人」と呼ぶには互いの確認が必要で、その言葉自体が呼びかけにはならない。逆に「知り合い」であることは多くの場合すでに事実であり、こちらもあえて相手に呼びかける意味はない。「友だち」だけが、呼びかける。
だから、いつか恋人になりたいと思っている相手に「友だち」と呼ばれると、ショックを受けたりする。それが第一に、ある種の意思表示だからである。また上司が部下を、また先生が生徒を「友だち」と呼んだとしたら、そこにはかえって歪な権威性が見えてしまう。すなわち、本当は対等な関係ではないにもかかわらず、上司、あるいは先生という立場によって、見せかけの「対等」らしい関係を維持するよう命じるような意味あいが生まれる。これもまた、「友だち」という言葉の持つ、呼びかけの機能によるものだろう。
「友だち」と呼ぶとき、わたしたちは事前に約束することができない。だから、「友だち」という言葉を使うならば、意識していようといまいと、わたしたちは願い、そして賭けさせられる。自分の望む親しい関係を相手が受け入れてくれるように。取材のときわたしも、まさに願ったのだ。いなくなってしまった相手に対してできることは、せいぜい願うことしかない。だからかえっていま、それがしっくりきたのかもしれない。
ということで、こんな定義をしてみよう。
友だち:互いに親しみを抱いている関係の名前。ひるがえって、自分が相手に対して抱いている親しみを、相手もまた自分に対して抱いていてほしい、という願いをこめた呼びかけ。
さて、定義をするということにも、どこか似たような乱暴さがある。つまりは、「あなたがどう思っているかはわからないが、わたしはこのように思っている」という表明。普段の会話をする上ではやっかいものかもしれないが、しかし「友だち」という言葉がこれほどまでに飛び交っているのを見るに、わたしたちは案外、そのような勝手さをも平気で飲み込んでしまえるのかもしれない。誰かに向かって「あなたのことを友だちと思っていますよ」と呼びかけるように、世界に向かって「あなたのことをこんなふうに思っていますよ」と呼びかけることだってしていいはずだ。そう思えばこの連載も、少しは気やすい。
次を読む
プロフィール
向坂くじら(さきさか・くじら)
詩人、国語教室ことぱ舎代表。Gt.クマガイユウヤとのユニット「Anti-Trench」で朗読を担当。著書『夫婦間における愛の適温』(百万年書房)、詩集『とても小さな理解のための』(しろねこ社)。一九九四年生まれ、埼玉県在住。

