
東洋と西洋の狭間で――#6 ルイーズ・アードリック『赤いオープンカー』(1)
早稲田大学教授で翻訳家・アメリカ文学研究者の都甲幸治さんによる連載の第6回では、ネイティブ・アメリカンをルーツにもつ作家、ルイーズ・アードリックを取り上げます。1980年代、ニューアカデミズムにはまっていたという都甲さんは、どのようにしてアードリックの作品と出会ったのでしょうか? 本日と明日の2日連続更新です。
連載第1回から読む方はこちら
僕が「人文系ワナビー」だったころ
今ここではない世界に強く憧れていた。高校生のころ、浅田彰の『構造と力』(中公文庫)を読んでニューアカデミズムにはまり、その源流ということで、文化人類学者である山口昌男の『本の神話学』(中公文庫)や『歴史・祝祭・神話』(中公文庫)などを読んだ僕は、世の中にこんなに面白い学問があるのか、と思って圧倒されてしまった。とにかく80年代の山口昌男はものすごく輝いていた。世界中の有名な知識人と対談し、ありとあらゆる本を読み、様々なテーマを論じ、歴史学から社会学、文学まで、複数の学問領域の垣根を飛び越えて、とても刺激的な議論をしていた。しかも本当に世界を巡っている。すごい。当時の僕にとって勉強といえば受験勉強だけで、だからこそ、こうした学問のスタイル、というよりライフスタイルに憧れた。まるでロックスターのようではないか。
だから大学に入ると、文化人類学者の船曳建夫先生がやっていた「儀礼・演劇・スポーツ」ゼミに入った。そして、レヴィ゠ストロースに直接質問した話や、パリの地下鉄でミシェル・フーコーに出会った話を先生から聞いてわくわくした。要するに、僕も典型的な人文系ワナビーだったというわけだ。こうした過去を僕は否定していない。というか、こういう時期があって良かったと思っている。当時は思いっきり背伸びして、次々に様々な本を読んでいたし、いろんな先生に会いに行って話を聞いたりもした。
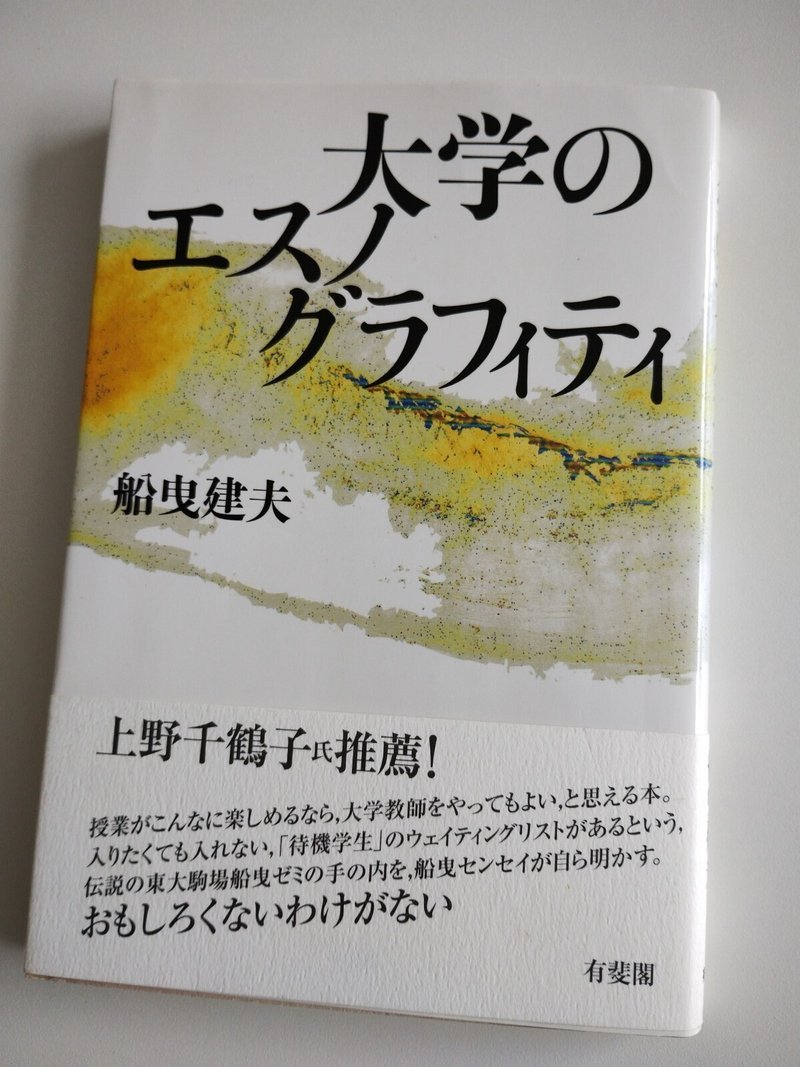
内的な魂の時間
さて3年になり、具体的に大学での専攻を決める、というところで困ってしまった。確かに文化人類学に進むことも考えてはみたが、なんというか、僕は田舎に弱いのだ。自然と親しんだこともないし、極端に日本と違う環境に適応できる自信もない。というわけで、そんなに激しく外国に行かなくてもできる文化研究ということで、表象文化論に進学した。結局、この学科も全然合わなくて、当時たまたま出席していた柴田元幸先生のアメリカ文学の授業にすがる形で、のちに現代アメリカ文学専攻に変わるわけだが、それはまた別の話である。

文化人類学には進学しなかったものの、そうしたものへの興味は依然として続いていた。そのころ、中沢新一がカルロス・カスタネダという人類学者について書いているのを読んで、この不思議な人物にどっぷりハマってしまった。『ドン・ファンの教え』(太田出版)や『未知の次元』(講談社学術文庫)といった著作には、メキシコの呪術師ドン・ファンに弟子入りし、ペヨーテなど幻覚性の植物を用いながら、ネイティブ・アメリカンの古来の知恵に彼が参入していく過程が描かれていた。我々が当たり前だと思っている現実がある。そこでは空間は均等に広がり、時間は時計通りに進む。だがそうではない、内的な魂の時間のようなものがある。そこに自由に入っていき、知恵を得て戻ってくる、という神秘的な修行の過程が彼の著作では描かれていた。
それは事実か、フィクションか?
当時の僕はビートジェネレーションやニューエイジ的なノリが大好きだったから、カスタネダの著作には強く魅了された。そして次々読破した。そのころは多くの作品の日本語訳が入手できたのだ。英語でも読んだ。そして呪術用語など、不必要な英単語をたくさん覚えた。白人の入植者たちに迫害されていたネイティブ・アメリカンたちが、実はこんな、数万年にもわたる深遠な叡智を受け継いでいた、ということに驚愕し、彼らにロマンチックな憧れを抱いた。
ご存知の方もいるかもしれないけれども、カスタネダの一連の作品は、今ではフィクションとして受け止められている。多少のフィールドワークには基づいているかもしれないが、むしろ彼が多様なものから刺激を受けて編み出した、ファンタジー的な物語だとされているのだ。確かに、苦労して魔法使いに出会い、弟子入りして、新たな知恵を得て生まれ変わり、現代社会に戻ってくる、という構造自体がジブリ的というか、ものすごくお伽噺っぽい。それでも、当時かなり素朴だった僕は、その多くが実話なんじゃないか、いや、そうであってくれ、なんて思っていた。まあ、このことを考えても、文化人類学者にならなくてよかったのかもしれない。

自分を癒やすための「儀式」
その後いろいろあって、現代アメリカ文学を専攻することになった僕は、いつしかネイティブ・アメリカンへのロマンチックな憧れを忘れてしまっていた。それを思い出したのは、30歳を過ぎて、ロサンゼルスにある南カリフォルニア大学に留学した後のことだ。ベトナム人のヴィエト・タン・ウェン先生のもとで、アジア系を中心としたアメリカのマイノリティ文学をいろいろと読む授業を取った。そこで出会ったのがレスリー・マーモン・シルコウの『儀式』(講談社文芸文庫)である。
この作品には衝撃を受けた。何と言ったらいいか、カスタネダの作品に登場する、古代の知恵を今も保った素晴らしいネイティブ・アメリカンとは全く違う人々が描かれていたのだ。もちろん、口承文化に満ちた彼らの生活は出てくる。だが現代社会の中で、彼らの人生はまったく変わってしまった。たとえば主人公のテイヨだ。ニューメキシコ州に住むネイティブ・アメリカンであるラグーナ・プエブロの血を引く彼は、第二次世界大戦で兵士としてフィリピンに送られ、日本軍の兵士と戦わされる。だが、日本人たちはあまりにもテイヨの親戚に顔が似ていて、容易に銃で撃てない。
そもそも、白人たちが支配するアメリカの戦争に、なぜ自分たちが駆り立てられ、見た目が近い有色の人々と戦わなければならないのか。テイヨは戦争で深く心に傷を負い、PTSDを発症する。帰国後、戦争の記憶に苦しみ続けるが、呪術医(メディシン・マンとも呼ばれる)は彼の病気を癒やすことができない。なぜなら、近代的な武器を使った戦争の傷に対処できる手立てなど、伝統的な呪術には存在しないからだ。結局テイヨは自分を癒やすことができる儀式を自分で見つけ出すしかない。数々の冒険の末、彼はなんとか日常に生還する。だが、すべての人がこんな偉業を成し遂げられるわけでもない。
隣人としてのネイティブ・アメリカン
1948年生まれでアングロ・サクソンとラグーナ・プエブロの血を引くシルコウが描くネイティブ・アメリカンたちは強く、そして悲しい。長年、彼らが狩猟をしてきた土地は、白人たちの農場によってフェンスで区切られてしまった。白人が作ったインディアン学校で教育を受けた彼らは、徐々に自分たちの文化を忘れてしまっている。だが、そうやってどんなに白人のふりをしても白人にはなれず、したがって差別を免れることはできない。新しくなってしまった世界の中で、自分たちらしい生き方をどうやったら手に入れられるのだろうか。
シルコウの描くネイティブ・アメリカンたちは、東洋の伝統文化と西洋文化の狭間でなんとか生き延びようと模索し続けている日本人の姿にも重なる。僕は『儀式』に登場する人々に強い共感を覚えた。そして僕の中で、ネイティブ・アメリカンたちはロマンチックで遠い存在から、現代社会に生きる身近な人々へと姿を変えた。
オジブウェの兄弟と「赤いオープンカー」
ネイティブ・アメリカンであるオジブウェの血を引くルイーズ・アードリックの名作短篇を集めた『赤いオープンカー』の表題作も、戦争から帰ってきたネイティブ・アメリカンの男性の話である。ただし、『儀式』のテイヨが行ったのが第二次世界大戦だったのに対して、「赤いオープンカー」のステファンが経験したのはベトナム戦争だ。
物語の中心となるのは、オジブウェの兄弟である。語り手の青年マーティは兄のステファンととても仲が良い。共同でお金を出し合って赤いオープンカーを買い、様々な場所を訪れる。途中で出会ったネイティブ・アメリカンの少女スージーを乗せてあげ、家まで送ると申し出るが、彼女の家はなんとアラスカだった。そのまま3人は遠くアラスカへ向かい、少女のコミュニティに温かく迎えられる。
変わり果てた兄の姿
だがこうした充実した日々は、ステファンの海兵隊入隊と共に過ぎ去る。戦争から戻ってきたステファンは、昔のように明るくジョークを言うことをやめ、陰鬱な顔でじっとテレビを眺めている。たまに笑ったとしても、喉が詰まったような叫び声を上げるだけだ。もはや弟と車を乗り回すこともない。
弟はテレビに細工して番組が映らないようにする。それだけではなく、なんと兄から託されていたオープンカーをこっそり、自分の手でめちゃくちゃに壊す。そして、兄貴が戦争に行っているあいだに乗り回していたら、こんなにボロボロになっちゃったよ、という。ステファンは怒ることなく、一つ一つの部品を手に入れながら、コツコツとオープンカーを直す。そうしているうちに、だんだんと正気を取り戻していく。よかった、ステファンはようやく心の傷を乗り越えることができたんだ、と弟は思う。
やがて2人は川へ遠乗りに出かける。だが、明るく歌い踊っていたステファンは突然、川に入り、そのまま姿を消す。兄の死を目の当たりにした語り手は、エンジンをかけたまま赤いオープンカーを川に沈めてしまう。
明日に続きます。お楽しみに!
題字・イラスト:佐藤ジュンコ
都甲幸治(とこう・こうじ)
1969年、福岡県生まれ。翻訳家・アメリカ文学研究者、早稲田大学文学学術院教授。東京大学大学院総合文化研究科表象文化論専攻修士課程修了。翻訳家を経て、同大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻(北米)博士課程修了。著書に『教養としてのアメリカ短篇小説』(NHK出版)、『生き延びるための世界文学――21世紀の24冊』(新潮社)、『狂喜の読み屋』(共和国)、『「街小説」読みくらべ』、『大人のための文学「再」入門』(立東舎)、『世界文学の21世紀』(Pヴァイン)、『偽アメリカ文学の誕生』(水声社)など、訳書にチャールズ・ブコウスキー『勝手に生きろ!』(河出文庫)、『郵便局』(光文社古典新訳文庫)、トニ・モリスン『暗闇に戯れて――白さと文学的想像力』(岩波書店)ドン・デリーロ『ホワイト・ノイズ』(水声社、共訳)ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(新潮社、共訳)など、共著に『ノーベル文学賞のすべて』(立東舎)、『引き裂かれた世界の文学案内――境界から響く声たち』(大修館書店)など。

関連書籍
都甲幸治先生といっしょにアメリカ文学を読むオンライン講座が、NHK文化センターで開催されています。
NHK文化センター青山教室:1年で学ぶ教養 文庫で味わうアメリカ文学 | 好奇心の、その先へ NHKカルチャー (nhk-cul.co.jp)
NHK文化センター青山教室:1年で学ぶ教養 英語で読みたい!アメリカ文学 | 好奇心の、その先へ NHKカルチャー (nhk-cul.co.jp)

