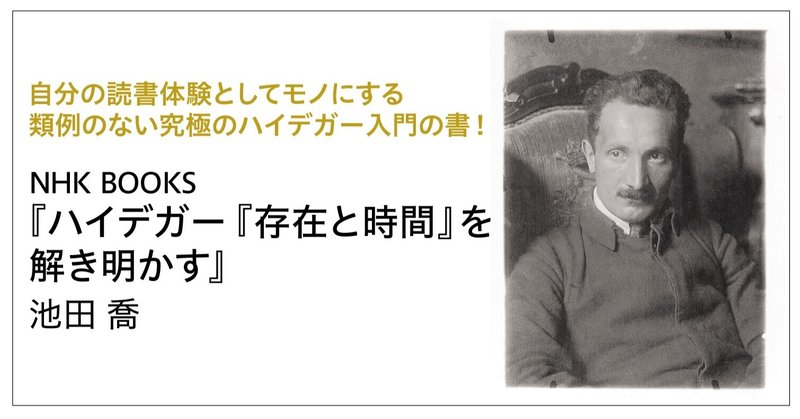
ハイデガーは高尚でも非実用的でもない。今日を生きる私たちの「心の拠り所」である
あの「哲学書の最高峰」が今度こそ踏破できる!
現代哲学最高峰の勘所をつかむ――全章が平易な「問いかけ」で構成され、難解だった文章が手に取るようにわかってくる。9月25日発売のNHK BOOKS『ハイデガー 『存在と時間』を解き明かす』は、実力派の新鋭による“はじめてのハイデガー” に触れられる一冊です。凝り固まった世界観を根底から問い返して、「自分本来の生き方」を浮かび上がらせてくれる新方式の画期的な入門書。当記事では、本書よりその序文をお伝えします。
一九二二年、三十三歳になる年、マルティン・ハイデガー(一八八九-一九七六)は、南ドイツのいわゆる「黒い森(シュバルツバルト)」のトートナウベルクという地に、わずか三部屋からなる山小屋を建てた。彼は晩年までこの山小屋に好んで滞在し、ここで執筆した。一九三三年に、ドイツ最大の都市にあるベルリン大学から二度目の招聘を受けたときにも応じなかった。その年の秋、ハイデガーはラジオ講演「なぜわれらは田舎に留まるか?」でこう語った。「冬の真夜中に、激しい雪嵐が小屋の周りに吹き荒れて、すべてを覆い尽くすとき、そのときが哲学の絶頂期である」、と。
ハイデガーの主著『存在と時間』は、彼がこの山小屋を建ててから五年後、このラジオ講演から六年前の一九二七年に出版された。その後二十世紀最大の哲学書という名声を得ることになったこの本は、「存在の意味とは何か」という巨大な問いに取り組むものだ。世界を見渡してみれば、人間、動物、植物、人工物、天空、大地など、実にさまざまなものが存在している。存在の意味を問うためには、存在者の領域の一部を探究するのではなく、およそ何かが何かとして存在するとはどういうことかを全面的に探究しなくてはならない。この大規模な思考は、「存在者の存在についての学」としての「存在論」と呼ばれもする。
『存在と時間』はなぜ難解と言われながらも、読者を獲得し続けているのか。『存在と時間』は、抽象的で大規模な存在論の思考を、各自が世界の内に存在する具体的なあり方に密着して展開する。工具を用いて家を補修したり、自室で机に座り何かを書き留めたり、台風が来ると聞いてそのときに備えたり、ニュースで他人の死について見聞して自分の死を恐れたり、日が暮れると仕事をやめて家に帰ったり、自分はどのようにありうるのかを問いながらこれまでの自分を振り返ったり……。これらはどれも本書で取り上げる『存在と時間』の具体例だ。ハイデガーは、私たちが存在する基本的なあり方は「世界内存在」だとしたが、その際、それは世界の内に「住まう」とか「滞在する」という意味で言われている。山小屋を愛したハイデガーは、存在論を、アカデミズムの概念遊戯から、あるいは大学という限定された空間から、日々の暮らしのただなかに引きずり出した。それは、存在の意味への問いという途方もない問いを、存在への問いを忘却してしまった現代の読者のなかに呼び覚まそうとする『存在と時間』の戦略の一部だった――。
『存在と時間』の難解さと親しみやすさ
存在とは何か。『存在と時間』のこの問いは、ほとんどの人が一度も問わずに死んでいくような、荘厳な(?)哲学的問いの典型だろう。この問いに比べれば、「心とは何か」とか「正しい行為とは何か」といった問いのほうが身近に感じられるかもしれない。他方で、『存在と時間』を読み進めてみると、誰もが過ごしているような身近な日常生活が細やかに観察され分析されていることに気がつく。さらに、多くの人が生きていくなかで抱く切実な関心事が正面から論じられていることに、強い印象を受けるはずだ。心のあり方を行動主義とか心脳同一説といった言葉で説明する哲学や、道徳的行為について功利主義とか義務論とかいった枠組で論じる哲学よりも、多くの読者が『存在と時間』に独特な親近感を覚えてきた。次のことを考えてみてほしい。
○ 存在の意味とは何か。このような問いに頭を悩ませるのは、普通の人には無縁な知的ゲームのように聞こえるかもしれない。しかし、あなたが存在することにとって、あなた自身の存在は重要で大切なことがらである。あなたの存在はあなた自身のものであり、誰のものにも代えは利かない。このように言われたらどうだろうか。(このような仕方で存在するあり方をハイデガーは「実存」と呼ぶ。)
○ 個々に存在しているものではなく、世界それ自体は存在しているのか。こう問われれば、とてつもなく抽象的で現実から浮遊した問いだと思うかもしれない。しかし、人は不安に襲われるとき、何もかもが――つまり、個々の存在者ではなく世界が全体として――疑わしくなり、世界がまったく無意味になる、と言われたらどうだろうか。
○ 伝統的な存在論における、実体、性質、様相といった用語は、普通の生活で使われる語彙からはあまりにも隔たっていると感じるだろう。では、実存、不安、存在の重荷、死への先駆、良心の呼び声といった言葉遣いについてはどうだろうか。
『存在と時間』には、難解で抽象的と言われる面と、身近で具体的と言われる面が同居している。だからだろう。『存在と時間』は、出版以来ずっと、世界各地の哲学者の深い読解の対象になると同時に、哲学の専門家ではない幅広い読者にとっても気になる書物であり続けている。この二面性は何よりも出版事情によく現れている。一方で毎年のように専門的な研究書が出版され、論文も数多く公刊されている。(私はフランスのハイデガ―専門誌『Bulletin Heideggérien』に二〇一一年の創刊以来、毎年、日本で出版されたハイデガ―関連の学術論文と書籍のリストを作成して提供してきたが、提出時期が近づくと気が重くなる。作業量が多すぎるのだ。)他方で、一般読者向けの入門書も次々に刊行されている。日本では同じ出版社の同じシリーズに少しだけタイトルを違えた『存在と時間』入門書が複数あるくらいだ。もっとも、入門書の豊富さということはカントについても言えるかもしれない。だが、圧倒的なのは翻訳書の量であり、『存在と時間』の日本語の翻訳書は十冊を超える。また最近の翻訳書のなかには、全パートについて詳細な解説を加えた、注釈書(コメンタリー)に近いスタイルのものも複数ある。『存在と時間』を学びたいのであれば、そのための情報源はすでに読み切れないくらいある。
なぜ、なおも『存在と時間』について書くのか
本書もまた『存在と時間』への一つの入門書であろうとしている。いったい、入門書のすでに十分に長いリストをさらに長くする必要があるのか。なぜそんなことをしようとするのか。
簡潔に言えば、『存在と時間』を開いて少し読めば、あるいは、『存在と時間』について見聞きしたときに自然と湧き上がるような疑問に、きちんと答えていきたいと思うからである。たとえば、『存在と時間』は大工がハンマーで釘を打つ場面の分析を長々としているが、なぜそのようなことが存在論をやっていることになるのか、なぜ『存在と時間』の言葉遣いはかくもほかの哲学書と違うのか、『存在と時間』は倫理について何を言えるのか、未完の『存在と時間』は結局何をどこまで成し遂げたのか、などなど……。もちろん、数ある入門書はどれも質が高く、これらの疑問にそれぞれの仕方で答えているであろう。だが、本書がほかの入門書と違うのは、こうした疑問が章のタイトルを構成し、疑問を解き明かすことを通してテキストを読解する、という点である。とはいえ、それらの疑問はランダムに並んでいるのではなく、『存在と時間』の章立ての順序におおよそ従っている。その結果として、『存在と時間』の重要概念をかなりの範囲にわたってカバーし、全体像を明らかにしている。
「問い」から始めるというやり方は、哲学や倫理学の授業をそれなりの間担当してきたなかで自然と身についてきたものだ。最初は、たとえば哲学概論であれば、教科書的に(というより、実際に教科書を使って)、プラトンから始まって徐々に時代が新しくなって最後は現代哲学で終わるといった順序の授業をしていた。あるいは、倫理学概論であれば、これも教科書的に、功利主義、義務論、徳の倫理学といった代表的な学説を順次解説していく、といった授業をしていた。ところが、もしかするとこうしたやり方は「入門」にはあまり向いていないのではないかと思い始めた。なぜなら、このやり方は、代表的な哲学者や主義主張がどういうものであるかを私が解説し始める前から、受講者があらかじめそれらに対して関心をもっていることを前提しており、それゆえある意味ではすでに「入門済み」の人を対象にしているように思えたからである。それ以降、たとえば、「死刑は認められるか」という問いをベースにして、義務論や功利主義の立場に言及し、結果的に、全体として倫理学の代表的学説をカバーする、というやりかたを目指し始めた。『存在と時間』という一冊の本への入門においても、この本について少し見聞きしたくらいの人でも共有できる問いから始めて、個別の概念や議論に触れていく、という順序で話をするほうが効果的であるように思えたし、そう考えると、そういうタイプの入門書は案外ないことに気がついたのである。
ただし、本書は、『存在と時間』の概念と議論を完全に網羅しようとはしていない。これは簡単な決断ではない。研究者は、ほとんど強迫的に、一切の漏れなく網羅的に解説しなければと思うものだからだ。しかし、本書において私は、禁欲的であろうとした。なぜなら、もしこの欲求を本当に満たそうとするならば、その本は、各節について順次注釈をつけるようなコメンタリーになる以外にないと思うからである。幸いすでに、詳細なコメンタリーが全編にわたって付けられた翻訳書もある*。また、最近、ハイデガーの概念のほぼ完全網羅を目指したハイデガー事典も出版された**。だから、完全網羅を本書で目指す必然性は感じない。
また、多くの入門書がそうしているように、『存在と時間』の章立てに沿って順次解説を加えるというやり方もしていない(この路線を突き詰めると注釈付き翻訳に近くなると思う)。自然に生じる疑問に答えるという目的のなかで、『存在と時間』の大部分の概念をだいたい『存在と時間』の流れに沿ってカバ―する、というあたりを狙う。この本が目指しているのは、『存在と時間』にさまざまな角度からアクセスし、その内部に入り込み、内部を動き回る――そういう意味での「入門」である。大学キャンパスのように、内部に通じる門は大小さまざまに色々なところにある、というイメージだ。
これは一見、奇異なアプロ―チのように聞こえるかもしれないが、そうではない。思い浮かべてみてほしい。本を最後まで音読せよと言われれば、私たちは最初から最後まで順番に読んでいく。けれども、本を理解せよと言われれば、私たちはそのように進むのではなく、先をめくったり、前に戻ったり、冒頭の箇所は特に念入りに読んだりと、ムラのある読み方をする。それは、理解するという行為は、テキストをそのまま再現することが目的なのではなく、その議論の筋道を自分自身で見出し、その中身を自分自身で言い直せるように努めるものだからである。例えば、『存在と時間』の冒頭で「存在の意味への問い」がこの書のテーマとして提示されるが、本気で理解しようとするなら、「存在」や「問い」という言葉でハイデガーが何を言わんとしているのかだけでなく、「意味」とはなんのことかも気になるはずだ。ところが、存在や問いについては『存在と時間』の最初の二節でそれなりに説明されるが、「意味」については中盤の第三十二節に至るまで明確には説明されない。この本をきちんと読んだことのある人なら誰でも、『存在と時間』冒頭部を理解するためには、第三十二節の意味の規定が不可欠であることを知っている。そういう、読みの道筋を、まだこの本を読んだことのない(あるいは、今後も読むことはないが大体の内容を知りたい)読者に提示するのは、専門家が入門書でなすべき重要な仕事だと思う。意味とは何かについてのハイデガーの考えを知るのに、本を音読する時のように中盤まで待っている必要はない。むしろ、森の内部を探検することで、森の全体を自分の身体でもって徐々に把握していくように、『存在と時間』の内部を探検することで、その全体像を自分の頭によって切り開いていくことが重要だ。
『存在と時間』以外の資料の活用について
二十世紀の終わり頃から、『存在と時間』だけを読んで『存在と時間』を論じる研究者はほとんどいなくなった。なかでも、ハイデガーが亡くなる一年前から刊行の始まった『ハイデガー全集』には、『存在と時間』出版以前に行った講義の記録や未公刊資料が収められており、これらが『存在と時間』の成立の経緯をかなり明らかにしているからである。
多くの研究者が、これらの新資料に基づいて『存在と時間』を新たな角度から照らし出すことに注力している。私自身、そういう研究をしてもきた。しかし本書ではそれらの情報に触れることには禁欲的になり、『存在と時間』という一つの作品の内部にとどまって、この本を読むことにこそ集中したいと思う。というのも、『存在と時間』の舞台裏を『存在と時間』以外の資料から暴露するという(ジャーナリスティックとも言える)やり方は、実際のところ、『存在と時間』を読むという、当然の行為の重要性から目を逸らしていると感じるからである。舞台裏を見たからといってその作品を理解したことにはならない。作品自体をじっくりと見なくてはならないのだ。
それに、こうした暴露的アプローチは、『存在と時間』を読むだけでも骨が折れるのに、『存在と時間』を理解するには『存在と時間』を読むだけでは足りない、というメッセ―ジを読者に伝えてしまう。しかしこれは、『存在と時間』を理解するにはハイデガーの専門的研究者になるしかないと言っているのに等しく、ハイデガー研究者がこういうメッセ―ジを発するときには『存在と時間』へのアクセス権を自分たちで独占するという効果が生じてしまう。
逆に、『存在と時間』以外の資料から得られる重要な情報にまったく触れないというのも、今度は、ハイデガー哲学の研究成果を専門家内で占有するという結果につながりかねない。
こうしたアンビバレントな判断ゆえに、本書は次の方針をとる――『存在と時間』を読むという第一目的から離れないように、『存在と時間』本文との関連づけが容易かつ十分にできる場合だけ、『存在と時間』以外からの情報を活用する。『存在と時間』の軌道から外れないように、『存在と時間』以外の内容には深入りしない――。『存在と時間』以外の公刊著作や講義録については邦訳も含めて書誌情報を凡例に記した。読者がそれらの文献を手にとるきっかけになれば幸いだ。
一見斬新なスタイルをもつ『存在と時間』はもともとアリストテレスのテキスト解釈(という地味な〔?〕狙い)の書として構想され、ハイデガーのジャーゴンと言われてきた特徴的な用語の多くが実は彼の独創ではなく古代ギリシャ語からのドイツ語への翻訳によって獲得されていること。「住まう」こととしての世界内存在の分析は、四半世紀後に行われた有名な講演「建てること、住むこと、考えること」のような後期思想とも接続できること――。本書で述べるこれらの事実は、『存在と時間』を、「天才の独創的書物」として神秘化することなく、この書物をそれにふさわしい哲学史的文脈へと置き直すことに貢献するだろう。そして、『存在と時間』は完成品ではなくその後の思索の流れに引き継がれるべき一つの通過点として現れてくるに違いない。
それでは『存在と時間』の内部を動き始めよう。
* 『存在と時間(一-四)』熊野純彦訳、岩波書店、二〇一三年。『存在と時間(一-八)』中山元訳、光文社、二〇一五-二〇年。
** ハイデガー・フォ―ラム編『ハイデガー事典』、昭和堂、二〇二一年
※続きはNHK BOOKS『ハイデガー 『存在と時間』を解き明かす』でお楽しみください。
* * *
10/8(金)19時から、著者・池田喬さんとその盟友・古田徹也さんが登壇して、効率よく本書のポイントを解説するイベントが催されます。今年1月に200名超の視聴を集めた大好評イベントの“完結編”です!
プロフィール
池田 喬(いけだ・たかし)
1977年、東京都生まれ。東京大学文学部卒業、同大大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。明治大学准教授。ハイデガー『存在と時間』の読解を出発点に、「知覚」「行為」「自己」などの観点から、現象学を中心とした現代哲学・倫理学を研究する。著書に『ハイデガー 存在と行為――『存在と時間』の解釈と展開』(創文社→講談社)、共編著に『生きることに責任はあるのか――現象学的倫理学への試み』(弘前大学出版会)、『始まりのハイデガー』(晃洋書房)、『映画で考える生命環境倫理学』(勁草書房)など、訳書にハイデガー『現象学の根本問題』(虫明茂氏との共訳、創文社→東京大学出版会)など。

